日本語教師養成コラム
日本語教員試験と日本語教育能力検定試験の違いを詳しく解説
公開日:2025.03.26 更新日:2025.08.07

監修者情報
ルネサンス日本語学院 日本語教師養成講座講師
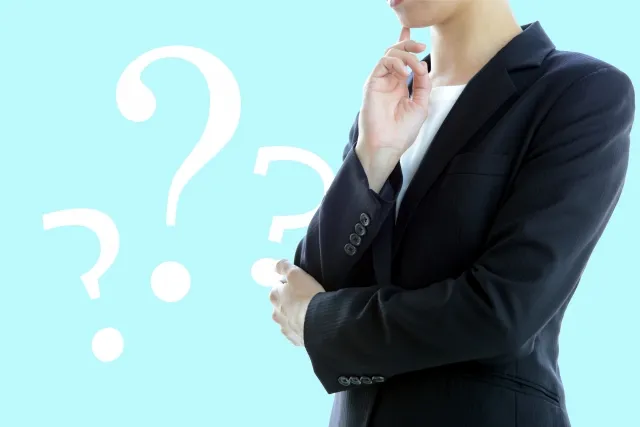
2024年4月から、日本語教育が文部科学省の管轄となり、関連する資格制度が大幅に変更されました。
従来の制度との違いに、「結局のところ、日本語教師になるためにはどうしたらよいの?」と戸惑っている方も、多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、日本語教師の登竜門ともいえる、日本語教員試験と日本語教育能力検定試験の違いについて徹底解説します。
日本語教師になりたいとお考えの方は、ぜひ参考になさってください。
- 日本語教師になる第一歩はこちら 資料請求
- 専任の担当者が回答します 個別相談・お問い合わせ
電話でのお問い合わせ・ご相談はこちら
日本語教員試験とは

日本語教員試験とは、今後日本語教師として働いていくために不可欠な、"登録日本語教員"の国家資格を取得できる試験のことです。
資格制度の変更後は、日本語教員試験に合格して、登録日本語教員の有資格者となった方のみが、認定日本語教育機関で働けるようになります。
現役で日本語教師として働いており、今後も続けていきたい場合には、2029年3月まで に日本語教員試験に合格し、登録日本語教員の国家資格を取得しなければなりません。
なお、この試験は日本語教師として働くにあたって、必要な知識が備わっているのかを判定する目的で行われています。
受験資格に制限はなく、受験料を支払えば誰でも挑戦できます。
<関連記事>【最新】日本語教員試験とは?試験内容や合格基準を解説
日本語教育能力検定試験とは

日本語教育能力検定試験とは、公益財団法人日本国際教育支援協会が毎年、年に1度(10月)に実施している民間試験のことを指します。
これまでに30回以上行われており、現在日本語教師として働いている人のなかには、受けたことがある方も多いのではないでしょうか。
その目的は日本語教員試験と同様に、日本語教育に携わるにあたって、必要な知識が備わっているのかを確認することです。
こちらも、受験資格に制限はありません。
<関連記事>【2023年度版】日本語教育能力検定試験の合格点・合格率の傾向を徹底解説
日本語教員試験と日本語教育能力検定試験の概要と違い
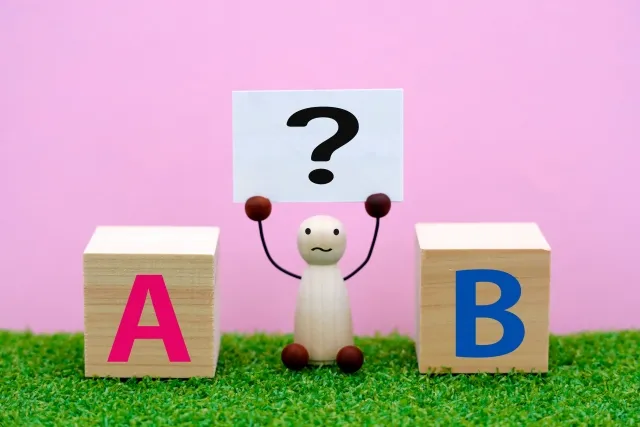
前項で日本語教員試験と日本語教育能力検定試験の大枠がわかったところで、次はそれぞれの概要と違いを確認していきましょう。
【 日本語教員試験と日本語教育能力検定試験の概要 】
|
|
日本語教員試験 |
日本語教育能力検定試験 |
|
実施している機関 |
文部科学省 2025年以降は法人 |
公益財団法人 日本国際教育支援協会 |
|
試験の構成 |
基礎試験 応用試験 |
試験I 試験II 試験III |
|
試験の時間 と問題数 |
基礎試験:マーク式100問120分 応用試験 聴解:マーク式50問50分 読解:マーク式60問100分 |
試験Ⅰ:マーク式100問90分 試験Ⅱ:マーク式40問30分 試験Ⅲ:マーク式80問 +記述400字120分 |
|
合格率 |
試験免除者も含むと約6割 (試験受験者のみ約4割) |
2~3割程度 |
両者はまず、実施している機関が異なります。
また、試験の構成や時間、問題数といった項目にも違いが存在します。
日本語教員試験は基礎と応用があり、さらに応用試験が聴解・読解の2種類に分かれているのが特徴です。
基礎試験については、文科省に認定された大学の講義もしくは、日本語教師養成講座を修了していれば免除され、応用試験の合格のみで登録日本語教員の資格を取得できます。
応用試験の時間は聴解が50分、読解は100分となっています。
一方で、日本語教育能力検定試験はⅠ・Ⅱ・Ⅲの3部構成です。
特筆すべきは試験Ⅲにおいて、言語の理解や、教育の内容に対する考えを問われる記述式の出題があるという点です。
マーク式の回答とは異なり、設問の要点をまとめて自分自身の考えを簡潔に述べる力が試されるため、個別に対策する必要があります。
<関連記事>日本語教育能力検定試験とは?合格ラインや勉強方法を解説
日本語教員試験と日本語教育能力検定試験の出題範囲

日本語教員試験と日本語教育能力検定試験にはさまざまな違いがありますが、出題範囲は共通しています。
【日本語教員試験と日本語教育能力検定試験の出題範囲】
- ・社会・文化・地域
- ・言語と社会
- ・言語と心理
- ・言語と教育
- ・言語
上記の出題範囲は、日本語教師の養成課程において指導される「必須の50項目」になっています。
これらを網羅することによって、日本語教師としての基盤となる知識が身につきます。
<関連記事>日本語教師を目指すのに役立つ本20選!試験対策や授業の教え方など
日本語教員試験の難易度

続いてご紹介するのは、日本語教員試験の難易度についてです。
2024年11月に行われた「日本語教員試験」第一回試験の合格率は、基礎試験から受けた全試験受験者が9.3%、応用試験のみの受験者が61.0%でした。
基礎試験の合格基準は「必須の教育内容で定められた5区分において、各区分で6割程度の得点があり、かつ総合得点で8割程度の得点があること」、 応用試験の合格基準は「総合得点で6割程度の得点があること」となっており、現職の日本語教師からも特に基礎試験の難易度が高かったという声があがっています。
今後の難易度の変化次第ですが、第一回目の日本語教員試験の結果からは、独学での「試験ルート」より基礎試験が免除となる「養成機関ルート」の方が国家資格取得に向けて確実なルートになることが予想されます。
<関連記事>日本語教師資格の難易度は?国家資格化による変更点
日本語教育能力検定試験の難易度
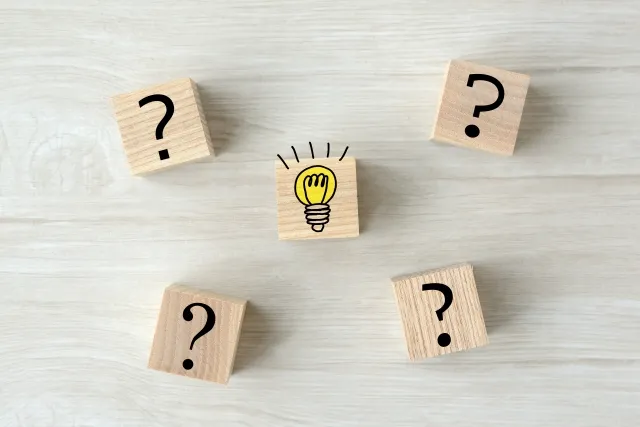
日本語教育能力検定試験の合格率は、例年3割程度しかなく、難易度の高さがうかがえます。
難易度を高めている要因としては、出題範囲の広さが考えられます。
また、年に1度しか実施されず、モチベーションの維持や計画的な学習が難しいことも関係しているのかもしれません。
しかし過去数年のデータを見ると、日本語教育能力検定試験の合格率は上昇傾向にあります。
【過去5年間の日本語教育能力検定試験の合格率】
|
年度 |
合格率 |
|
2024年度 |
30.9% |
|
2023年度 |
30.8% |
|
2022年度 |
30.8% |
|
2021年度 |
29.7% |
|
2020年度 |
28.8% |
試験対策講座や過去問を活用して、着実に学習を進めていけば、きっと合格できるはずです。
<関連記事>日本語教育能力検定試験に合格するために必要な勉強時間
- 日本語教師になる第一歩はこちら 資料請求
- 専任の担当者が回答します 個別相談・お問い合わせ
電話でのお問い合わせ・ご相談はこちら
どちらの試験を受けるべき?

ここまでの内容を踏まえて、本項では、日本語教員試験と日本語教育能力検定試験のどちらを受ければよいのかを解説します。
目的によって受けるべき試験が変わるため、ご自身が目指す働き方を実現できる試験を選んでください。
日本語教員試験で登録日本語教員の国家資格を取得しておいたほうが、今後選択できる働き方の幅は広がります。
なぜなら冒頭でお伝えしたように、登録日本語教員の資格を取得していれば、 認定日本語教育機関で働けるようになるからです。
民間試験である日本語教育能力検定試験にのみ合格しても、認定日本語教育機関では働けないため注意が必要です。
日本語教師として働きたい方は、日本語教師養成講座や対策テキストを活用して、日本語教員試験を受けてみてはいかがでしょうか。
次に、「日本語学校で働くかどうかは迷っているけど、資格を取りつつスキルアップを図りたい」とお考えの方には、日本語教育能力検定試験が向いています。
日本語教育能力検定試験を受ければ、日本語教育に関してある程度の知識が身につきます。
過去に30回以上実施されていることから、対策用のテキストや講座が豊富で、学習しやすい点も魅力的です。
くわえて、「いままでは考えていなかったけど、やっぱり日本語教師になりたい」と気持ちが変わったときにも、日本語教育能力検定試験は役に立ちます。
前述の通り、日本語教員試験の出題範囲は、日本語教育能力検定試験と共通しています。
そのため、登録日本語教員の国家資格を取得するにあたって、日本語教育能力検定試験の学習が有利に働くのです。
さらに認定日本語教育機関への応募の際、ご自身のスキルの証明となり、基本給のアップにつながる可能性もあります。
以上のことをまとめると、将来の選択肢に差はあるものの、日本語教員試験と日本語教育能力検定試験のあいだに優劣はないことがわかります。
どちらの試験を受けても、日本語を教える立場として成長できることは間違いないでしょう。
<関連記事>「日本語教育能力検定試験は役立たない」は本当なのか?
登録日本語教員の資格を取得するためのルート
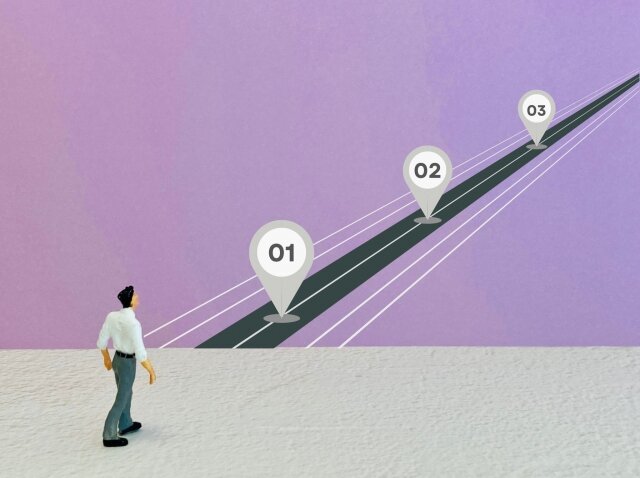
最後に、今後の選択肢を増やせる、登録日本語教員の有資格者になるまでの流れを状況別に解説します。
各ルートの特徴は、以下の通りです。
【登録日本語教員の資格を取得するための各ルートとその特徴】
- ・ルート①:大学・日本語教師養成講座へ通わずに自分で学ぶ
- ・ルート②:実践研修も行っている大学や民間の登録日本語教員養成課程で学ぶ
- ・ルート③:実践研修を行っていない大学や民間の登録日本語教員養成課程で学ぶ
ご自身の状況と照らし合わせて、日本語教師になるためにはどのルートをたどればよいのか、ご確認ください。
ルート①:大学・日本語教師養成講座へ通わずに自分で学ぶ
ルート①では、専門の大学や民間の日本語教師養成講座へ通わずに、以下3つのステップを踏んで登録日本語教員の資格を取得します。
【 ルート①で登録日本語教員の資格を取得するまでに必要なステップ】
- 1.日本語教員試験の基礎試験に合格する
- 2.日本語教員試験の応用試験に合格する
- 3.登録実践研修機関で教育実習を受けて、修了する
大学や養成講座で学ばないぶん、日本語教師になるためにご自身での準備が、ほかのルートよりも多くなるのがルート①の特徴です。
メリットとしては、ほかのルートに比べると、費用を抑えながら登録日本語教員の資格を取得できることが挙げられます。
ルート①は独学で資格の取得を目指すため、支払うのは日本語教員試験の受験料と、登録実践研修機関の費用だけで済みます。
一人で計画的に学習を進めていく自信があり、少しでも費用の負担を減らしたい場合には、ルート①を検討してみてもよいかもしれません。
ただし、ルート①で日本語教師を目指すのは、非常に難易度が高いという点にはご留意ください。
日本語教員試験は新しい試みであり、過去問が揃っていないのはもちろん、対策テキストも充実していないのが現状です。
このような状態では、一人で進められる学習にも限界があります。
以上のことから、登録日本語教員の資格を取得する場合は、後述のルート②ルート③を選択するのがおすすめです。
<関連記事>日本語教師になるための資格取得費用を抑える方法と金額の目安
<関連記事>【2025年最新版】日本語教師になるには?仕事内容や、向いている人について解説!
ルート②:実践研修教育実習も行っている大学や民間の登録日本語教員養成課程で学ぶ
ルート②においては、実践研修まで行っている大学や民間の登録日本語教員養成課程で勉強したのちに、日本語教員試験を受けます。
このルートの最大の特徴は、事前に実践研修まで済ませることによって、あとは日本語教員試験の応用試験に合格するだけで日本語教師になれるという点です。
養成課程で、基礎試験の合格に相当する知識と技能を身につけているため、応用試験の学習も比較的スムーズに進めることができます。
「多少の費用や時間がかかっても、より確実な方法で登録日本語教員の資格を取得したい」という方には、ルート②が向いています。
また、ルート②で日本語教師養成講座を選ぶ際には、補助制度についてもあわせて確認しておきたいところです。
まずは、"リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業"の対象講座であるかどうかを確かめましょう。
この事業は経済産業省が実施しているもので、受講料の最大70%を補助してもらえます。
補助を受けるための条件は、在職者であり、講座の修了後に雇用主の変更を伴う転職を目指していることです。
上記の条件に当てはまらない離職中の方も、教育訓練給付金を受け取れる可能性があります。
これは厚生労働省の政策で、教育訓練給付制度の受給資格を満たし、指定された期間内で講座を修了した場合に支給される給付金です。
お住まいの管轄のハローワークに申請することで、受講費用の20%(最大10万円)ぶんの給付金が支給されます。
ルート③:実践研修を行っていない大学や民間の登録日本語教員養成課程で学ぶ
ルート③は、実践研修を行っていない大学や民間の登録日本語教員養成課程で勉強してから、日本語教員試験と実践研修を受けるというものです。
ルート②と同様に、日本語教員試験の基礎試験は免除されますが、応用試験に合格してから実践研修を行う必要があります。
なお、ルート②にも共通していますが、日本語教員試験の応用試験は、日本語教員養成過程が修了見込みの段階から受けることができます。
合格した年度の翌年4月までに養成過程の修了証明書を提出すれば問題ありません。
日本語教員試験と日本語教育能力検定試験の違いは国家資格を取得できるかどうか

今回は、日本語教員試験と日本語教育能力検定試験の違いを詳しく解説しました。
日本語教員試験は基礎試験と応用試験に分かれており、認定日本語教育機関で働くために必要な登録日本語教員の国家資格を取得できます。
対して、日本語教育能力検定試験は3部構成で、登録日本語教員の資格は取得できないものの、日本語教育に関する基礎的な知識が身につきます。
日本語教員試験の前に受験すれば、試験対策にもなるでしょう。
どちらの試験を受けるのかは、国家資格を取得したいかどうかで決めるのがよいと思います。
また、基礎試験を免除して国家資格を目指したい方は、ルネサンス日本語学院にお問い合わせください。
応用試験のみで国家資格取得を目指せる "登録日本語教員養成・実践研修コース"をご用意しておりますので、効率的に登録日本語教員の資格を取得できます。
日本語教師養成講座ならルネサンス日本語学院にぜひお問い合わせください。
この記事の監修者

ルネサンス日本語学院 日本語教師養成講座講師
《資格》日本語教師養成課程修了・日本語教育能力検定試験合格
《経歴》日本語教師養成講座を修了後、約30年に渡り、大使館、留学生、インターナショナルスクール、企業などで日本語教育に従事。また、(社)国際日本語普及協会の「地域日本語教育コーディネーター研修」修了後は、地域の日本語教育、ボランティア支援や教育委員会日本語研修プログラム、NHK文化センター、一部上場企業などへの日本語教育コーディネイトや日本語教師養成に携わり、日本語教育総合支援など多方面で活躍中。
《専門分野》就労者・生活者・年少者に対する日本語教育。
《監修者からのコメント》
日本語教師の勉強は、「知識」だけでも、「技術」だけでもだめです。 両方揃って初めて「学習者」という同乗者が安心して授業を受けられます。単なる知識の講座ではなく、皆さんより少し先を歩く私たち現役日本語教師が考え、悩み、苦労してたどり着いた答えを多く取り入れた「現場目線」を意識しています。
私自身、国語教師を目指し、日本語の文法にも自信があったにもかかわらず、「こんにちは。」の使い方を外国人に教えられなかった…というショックから、「日本語」に興味を持ち、日本語教師になりました。日本語教育業界は、わかりやすそうでわかりにくいですから、この業界の専門知識のある人に相談することがおすすめです。ぜひお気軽にお問い合わせください。
- 日本語教師になる第一歩はこちら 資料請求
- 専任の担当者が回答します 個別相談・お問い合わせ
電話でのお問い合わせ・ご相談はこちら
※学院生の皆様はマイページ
「事務局への質問」から
お問い合わせください。
平日・土曜 9:30-18:00


