日本語教師養成コラム
日本語教育能力検定試験とは?合格ラインや勉強方法を解説
公開日:2023.05.26 更新日:2025.06.13

監修者情報
ルネサンス日本語学院 日本語教師養成講座講師

日本語教育能力検定試験とは、日本語教育を行うために必要な基礎的な知識や能力があるかを問う内容で構成されている試験です。
公益財団法人日本国際教育支援協会が実施し、毎年10月に全国で実施しています。
日本語教師の就職先の一つである日本国内の法務省告示校、いわゆる日本語学校に勤める場合には、
日本語教育能力検定試験の資格を有していることが採用基準の一つになります。
2024年度からの制度で、日本語教師は国家資格「登録日本語教員」となり、
日本語教育を行う機関は文部科学大臣が認定する「認定日本語教育機関」となっていくことが決まりました。
参考サイト:https://www.mext.go.jp/content/20240321-ope_dev02-000034780_1.pdf
2025年現在はこの制度への移行期間中となっています。
国家資格としての登録日本語教員を取得するための試験ではないことに注意が必要です。
しかし、この試験に合格するメリットもありますのでどうぞご覧ください。
日本語教師は日本語学校で勤務するケースも多いため、日本語教育能力検定試験に合格することは、
日本語教師として働く上での大きなメリットです。
また、日本語教育能力検定試験に合格することで、客観的に自らの日本語教育に関する基礎的な知識と能力が
一定の水準に達していることを証明できるという点もメリットといえます。
電話でのお問い合わせ・ご相談はこちら
日本語教育能力検定試験とはどんな試験?

日本語教育能力検定試験とは、日本語教育を行うために必要な基礎的な知識や能力があるかを問う内容で構成されている試験です。
日本語教師の就職先の一つである日本国内の法務省告示校、いわゆる日本語学校に勤める場合には、
日本語教育能力検定試験の資格を有していることが採用基準の一つになります。
日本語教師は日本語学校で勤務するケースも多いため、日本語教育能力検定試験に合格することは、
日本語教師として働く上での大きなメリットです。
また、日本語教育能力検定試験に合格することで、客観的に自らの日本語教育に関する基礎的な知識と能力が
一定の水準に達していることを証明できるという点もメリットといえます。
<関連記事>【2023年度版】日本語教育能力検定試験の合格点・合格率の傾向を徹底解説
<関連記事>日本語教師は英語スキルがあった方が良い?あるとどんな時に役立つ?
日本語教育能力検定試験を受ける目的

日本語教育能力検定試験を受ける目的は、自らの日本語教育に関する基礎的な能力・知識が一定の水準に達しているかを
テストという形で測り、日本語教育を行うために必要な能力が備わっていることを証明することです。
<関連記事>【2025年最新版】日本語教師になるには?仕事内容や、向いている人について解説!
<関連記事> 日本語教師の基礎知識
日本語教育能力検定試験の出題範囲
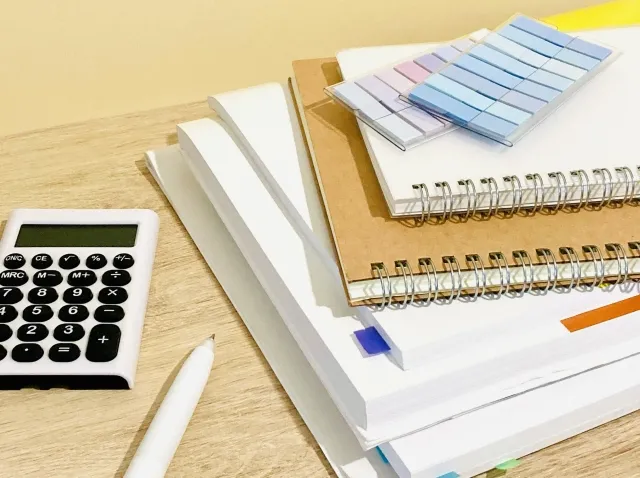
日本語教育能力検定試験では、"社会・文化・地域"や"言語と社会"など、出題範囲が5つの区分に分かれています。
詳しくは、下記の表をご覧ください。
【出題範囲】(令和4年度より) 次の通りとする。
ただし、全範囲にわたって出題されるとは限らない。
区分
主要項目
社会・文化・地域
①世界と日本
(1)世界と日本の社会と文化
②異文化接触
(2)日本の在留外国人施策
(3)多文化共生(地域社会における共生)
③日本語教育の歴史と現状
(4)日本語教育史
(5)言語政策
(6)日本語の試験
(7)世界と日本の日本語教育事情
言語と社会
④言語と社会の関係
(8)社会言語学
(9)言語政策と「ことば」
⑤言語使用と社会
(10)コミュニケーションストラテジー
(11)待遇・敬意表現
(12)言語・非言語行動
⑥異文化コミュニケーションと社会
(13)多文化・多言語主義
言語と心理
⑦言語理解の過程
(14)談話理解
(15)言語学習
⑧言語習得・発達
(16)習得過程(第一言語・第二言語)
(17)学習ストラテジー
⑨異文化理解と心理
(18)異文化受容・適応
(19)日本語の学習・教育の情意的側面
言語と教育
⑩言語教育法・実習
(20)日本語教師の資質・能力
(21)日本語教育プログラムの理解と実践
(22)教室・言語環境の設定
(23)コースデザイン
(24)教授法
(25)教材分析・作成・開発
(26)評価法
(27)授業計画
(28)教育実習
(29)中間言語分析
(30)授業分析・自己点検能力
(31)目的・対象別日本語教育法
⑪異文化間教育とコミュニケーション教育
(32)異文化間教育
(33)異文化コミュニケーション
(34)コミュニケーション教育
⑫言語教育と情報
(35)日本語教育とICT
(36)著作権
言語
⑬言語の構造一般
(37)一般言語学
(38)対照言語学
⑭日本語の構造
(39)日本語教育のための日本語分析
(40)日本語教育のための音韻・音声体系
(41)日本語教育のための文字と表記
(42)日本語教育のための形態・語彙体系
(43)日本語教育のための文法体系
(44)日本語教育のための意味体系
(45)日本語教育のための語用論的規範
⑮言語研究
⑯コミュニケーション能力
(46)受容・理解能力
(47)言語運用能力
(48)社会文化能力
(49)対人関係能力
(50)異文化調整能力
日本語教育能力検定試験ではこのように、日本語教育の手法や日本語の文法的な知識だけでなく、
異文化への理解度など幅広い範囲で出題されていることがわかります。
日本語教育能力検定試験の構成と配点
日本語教育能力検定試験は、試験Ⅰ~Ⅲの3科目で構成されています。
それぞれの時間配分や配点、および測定内容は以下の通りです。
【試験の構成 】
科目
解答時間
配点
測定内容
試験Ⅰ
90分
100点
原則として、出題範囲の区分ごとの設問により、日本語教育の実践につながる基礎的な知識を測定する。
試験Ⅱ
30分
40点
試験Ⅰで求められる「基礎的な知識」および試験Ⅲで求められる「基礎的な問題解決能力」について、音声を媒体とした出題形式で測定する。
試験Ⅲ
120分
100点
原則として出題範囲の区分横断的な設問により、熟練した日本語教員の有する現場対応能力につながる基礎的な問題解決能力を測定する。
引用元:公益財団法人 日本国際教育支援協会 令和6年度日本語教育能力検定試験実施要項
試験Ⅰでは、日本語の教育者として押さえておくべき基礎的な知識が求められます。
先に紹介した出題範囲に沿って、日本語の知識だけでなく、日本語教育の歴史やコミュニケーション能力などの問題も出題されます。
試験Ⅱは、音声出題による聴解問題です。
日本語を学習する海外の方の発音や、問題解決に対するアプローチ方法などについて、音声を媒体とした形式で出題されます。
試験Ⅲは、記述式とマーク式を用いた試験で、配点100点の内訳は記述式が20点、マーク式が80点となっています。
記述式の問題では、言語にかかわる事象や教育実践の方法などに対する、ご自身の考えや主張が問われますので、それを400字程度でまとめましょう。
参照元:公益財団法人 日本国際教育支援協会 令和6年度日本語教育能力検定試験実施要項
日本語教育能力検定試験の合格ラインと受験人数は?
日本語教育能力検定試験の受験者数は、令和元年度から4年度までは減少していたものの令和5年度に盛り返しており、
合格率は年々上昇傾向にあります。
直近5年間である令和元年から令和5年までの、それぞれの数値を表にまとめました。
【実施年度別の受験者数と合格率】
|
実施年度 |
受験者数(人) |
合格者数(人) |
合格率 |
|
令和5年度 |
8,249 |
2,542 |
30.8% |
|
令和4年度 |
7,076 |
2,182 |
30.8% |
|
令和3年度 |
8,301 |
2,465 |
29.7% |
|
令和2年度 |
9,084 |
2,613 |
28.8% |
|
令和元年度 |
9,426 |
2,659 |
28.2% |
日本語教育能力検定試験の合格率は年々増加しており、令和4年度、5年度と、2年連続で30%台に乗っています。
ちなみに、10年前の平成26年度は23.6%でしたので、過去10年間で7.2%も合格率がアップしていることになります。
参照元:公益財団法人 日本国際教育支援協会 令和5年度 日本語教育能力検定試験 結果の概要
日本語教育能力検定試験は難しい?
日本語教育能力検定試験の合格率は年々上昇傾向にありますが、それでも30%前後という状況からすると、
決して簡単な試験ではないといえます。
すでに記事内で紹介した通り、日本語教育能力検定試験の出題範囲は、非常に広範囲です。
仕事や学業をこなしながら、限られた時間ですべての項目を網羅的に学習しようとすると、
一つひとつの学習内容が浅くなってしまい、合格ラインに届きにくくなるのでしょう。
試験の対策として、日本語教師養成講座や日本語教育能力検定試験対策講座の活用、
独学の場合は過去問題を繰り返し解くことなどが挙げられます。
基礎的な知識をしっかりとインプットし、かつ苦手分野に重点を置いて学習すれば、合格へ近づけるはずです。
日本語教育能力検定試験で合格するためのポイント
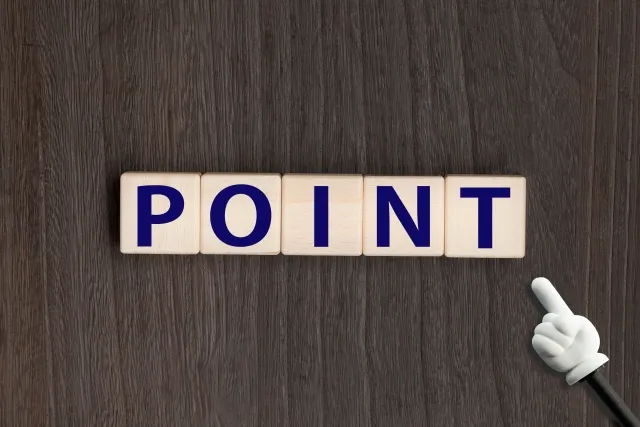
日本語教育能力検定試験に合格するためには、計画的な学習と知識のアウトプットが重要です。
ここからは、日本語教育能力検定試験に合格するために重要なポイントを3つ紹介します。
- ① 計画的な勉強スケジュールを立てる
- ② 過去問の演習で適度にアウトプットを行う
- ③ 試験対策講座を受講する
しっかりとポイントをおさえ、効率よく確実に合格を目指しましょう。
計画的な勉強スケジュールを立てる
日本語教育能力検定試験に合格するには、スケジュールを立てて計画的に勉強することが大切です。
たとえば、毎日何時間勉強するのか、どこで勉強するのかを決めておくとよいでしょう。
ただし、無理な計画を立てると挫折する可能性があり、楽過ぎる計画だとかえってやる気を失ってしまいます。
ご自身の生活スタイルを考慮したうえで、適度な負荷で無理なく勉強を続けられるようにするのがポイントです。
過去問の演習で適度にアウトプットを行う
日本語教育に関する基礎的知識が多く問われる日本語教育能力検定試験ですが、
一方的に知識を取り入れるだけでは、合格に必要な応用力が身につきません。
テキストなどで知識を取り入れたあとは、過去問を演習するなど、知識をアウトプットする時間を取りましょう。
過去問を解いていく過程で、自分に足りていない知識は何かも確認でき、効率よく学習が進められます。
また、合格への思いが強いあまり、多くの過去問教材を買ってしまうことがありますが、
知識の定着率を上げるためには、試験日までに確実にやり遂げられる適切な量の過去問教材を購入し、
限られた問題を繰り返し説きなおすことを意識しましょう。
検定対策講座を受講する
独学で勉強を進める場合は、自分の学習スケジュールを管理したり、必要な勉強量を着実にこなすだけの継続力が必要です。
しかし、試験の範囲は広く、聞きなれない専門用語も多く出てきます。
そのため、自分で管理するだけではうまく学習が進められないと感じる場合は、試験対策講座の受講を検討しましょう。
試験対策講座を取り入れることで、定期的な学習時間の確保と学習スケジュールの確立ができるだけでなく、
日本語教育の専門家である講座講師の分かりやすいポイント解説が聞けますし、
分からないところは講師に質問して理解できるまで教えてもらうこともできます。
電話でのお問い合わせ・ご相談はこちら
日本語教育能力検定試験に合格するメリット
ここでは、日本語教育能力検定試験に合格することで得られるメリットを2つ紹介します。
日本語教育の知識があることの証明になる
日本語教育能力検定試験に合格すれば、日本語教育の知識があることの客観的な証明になり、
日本語教育の職に就く際に有利にはたらきます。
日本語教師になるために、必ずしも合格していなければならないわけではありませんが、
「試験に合格していることが望ましい」と記載されている求人も少なくありません。
試験では、日本語教育についての基礎知識や、その知識を活かした現場対応能力が求められます。
合格することで、この知識や能力が定められた水準に達していると証明できれば、
採用側への大きなアピールポイントになるでしょう。
法務省告示校での採用基準の一つ
日本語教師が働く場としては、"法務省告示校"とよばれる、
政府の認可のもと運営されている留学生向けの日本語学校が挙げられます。
簡単に言うと、留学生がビザを取得できる日本語学校のことです。
法務省告示校は働ける学校数が多く、経営も比較的安定しており、
学ぶ熱意のある学生が多いといった教師側に好ましい条件がそろっています。
令和5年までの日本語教育能力検定試験に合格していることは、法務省告示校での採用の基準の一つです。
参考サイト:日本語教育機関の告示基準
今後は国家資格を取得していることが基本になり、
日本語教育能力検定試験の合格は追加であるとより良いという位置づけになっていくと考えられます。
また海外の日本語学校や、国内のビジネスマンを対象に教える日本語教師などにおいても、
法務省告示校と同様の採用基準が設けられている場合があります。
このように、日本語教育能力検定試験の合格は、将来の選択肢を広げる武器といっていいでしょう。
なお、2024年4月に施行された日本語教育機関認定法により、
改正前に法務省告示校として定められていた日本語教育機関も、新たに文部科学大臣の認定を受ける必要があります。
この新たな認定日本語教育機関は、2024年11月13日に公表されていますので、
現行の法務省告示校が上記認定を受けているのかご確認ください。
参照元:日本語教育機関認定法ポータル
参照元:日本語教育機関認定法 よくある質問集(令和5年8月時点)
日本語教育能力検定試験に受験資格はある?

日本語教育能力検定試験には必要な受験資格がなく、出願手続きを行えば誰でも受験できます。
国家資格ではないものの、国内の法務省告示校、いわゆる日本語学校が採用基準の一つとして設けている「文化庁届出受理日本語教師養成講座420時間コースを修了する」ことが難しい人にとっては、受験のハードルが低いことは大きなメリットといえます。
<関連記事>【日本語学校とは】日本語教師になりたい人必見!概要と就職するために必要な条件
日本語教育能力検定試験の出願手続きの基本的な流れ
日本語教育能力検定試験の出願手続きは、令和5年度からオンライン出願のみに変更されました。
これまでのように、郵送での出願はできませんので要注意です。
また、出願登録が可能な期間は、出願開始日の0時から出願最終日の23時59分までとなっています。
最終日はアクセスが集中し、Webサイトにつながりにくくなる可能性がありますので、
余裕をもって出願しておくのがおすすめです。
それでは、ここから、オンライン出願の流れを説明します。
アカウントを作成する
まずは、アカウント作成から始めます。
日本国際教育支援協会のWebサイトにアクセスし、日本語教育能力検定試験のページから、
さらに"オンライン出願サイト"へと進みます。
"新規登録"をクリックし、利用規約と個人情報の取り扱いに同意したあと、メールアドレスやパスワードなどを入力してください。
入力を終えて"登録"を押すと、仮登録のメールが届きますので、
60分以内にメールに記載されているリンクをクリックすれば、本登録完了です。
出願登録を行う
アカウントを作成できたら、次は出願登録です。
オンライン出願サイトのログイン画面を開いて、メールアドレスとパスワードを入力し"ログイン"を押すと、
メールで認証コードが届きます。
届いた認証コードを入力したら、ログイン完了です。
ログイン後は、オンライン出願サイトの"検定一覧"のなかから"日本語教育能力検定試験"を選択し、
"出願"より以下の必要事項を入力・確認します。
【出願に必要な入力・確認事項】
- ・留意事項などの確認
- ・試験名の選択
- ・受験希望地区の選択
- ・出願内容の確認
- ・出願者情報の入力、顔写真のアップロード
- ・出願者情報の確認
- ・アンケート入力と確認
受験希望地区については、試験会場の定員に空きがある場合に限り、出願後1回だけ変更が可能です。
変更を希望する場合は、変更が可能かどうかを日本国際教育支援協会に確認したうえで、
指定された期限までに必要書類を提出します。
ただし、同じ受験地区内での会場の変更には対応していませんので、覚えておきましょう。
また、出願者情報にて住所を入力する際は、受験票や合否結果通知書、
そしてなにより、合格証書を確実に受け取るために、入力ミスがないようにご注意ください。
登録できる住所は、日本国内にある住所のみです。
海外に居住している方が、一時的に帰国して試験を受ける場合は、
日本国内に住んでいる家族や知人宅の住所を入力してください。
出願後は、入力した住所を変更できませんので、転居した場合は郵便局へ転居届を出す必要があります。
受験料を支払う
必要事項の入力後は、受験料の支払方法を選択しましょう。
支払方法は、クレジットカード、コンビニ支払い、ペイジーのいずれかです。
クレジットカードを使う場合は、画面の案内に従って入力を進めていけば、その場で支払い完了です。
コンビニエンスストアやペイジーを利用する場合は、必要な番号が画面に表示されますので、
"お支払い情報送信"または"印刷"を選択して、番号を受け取ります。
番号を受け取ったら、それぞれの案内に従って支払いを済ませます。
支払い期限は、出願登録をした翌日から7日以内となっていますのでお忘れなく。
期限内にこれらの手続きを済ませたら、出願完了です。
なお、出願後は受験料を返金してもらえません。
登録内容の変更も出願取り消しもできませんので、くれぐれも入力ミスがないよう、最後にもう一度内容を見直しましょう。
また出願内容は、オンライン出願サイトの"出願内容一覧"から、いつでも確認できます。
日本語教育能力検定試験の出願手続きの流れ
日本語教育能力検定試験の出願方法は、令和5年度(2023年度)からインターネットによる受付へと変更されました。
(参考:JEES 日本語教育能力検定試験ホーム)
インターネット上で出願手続きを行った場合の支払方法には、
クレジットカード決済やコンビニエンスストア支払いなどのオンライン決済が用いられる予定です。
現時点ではインターネット上の出願手続きに関する詳細が告知されていませんが、
詳細については随時ホームページで告知される予定です。
本記事では、郵送で手続きを行う場合の出願手続きの流れについて、以下5つのポイントに沿って紹介します。
- ① 願書を購入する
- ② 写真を準備する
- ③ 支払いを完了させる
- ④ 願書を郵送する
- ⑤ 受験票を受け取る
それぞれ順に見ていきましょう。
願書を購入する
願書は書店かインターネット上で購入できます。
願書の購入には400円(2022年度実績)かかり、インターネットでは6月中旬ごろから販売が開始されます。
願書には「受験案内」「受験願書」「振替払込用紙(受験料を入金するための用紙)」「出願書類提出用封筒」の4点が入っています。
写真を準備する
日本語教育能力検定試験に合格した場合、合格証書にプリントされる写真を準備します。3か月以内に撮影した写真で、
縦40mm×横30mmの履歴書サイズで準備します。
写真を撮影する際には、顔がはっきり映るように、帽子やサングラスは着用しないように気をつけましょう。
支払いを完了させる
日本語教育能力検定試験の受験料は17,000円(税込)です。
支払方法には、郵便局の窓口で支払う方法と、ATMで支払う方法があります。
インターネットで手続きの場合、受験料の支払いは、
クレジットカード、コンビニエンスストア、Pay-easy によるオンライン決済が予定されています。
郵便窓口で手続きを行う際には、願書に同封されている「振替振込用紙」を使用して支払い手続きを行います。
ATMで振り込み場合には、ゆうちょ銀行ATMのみ利用できます。
願書を郵送する際、支払い完了を証明する書類も同封するので、
ATM振込の場合には、「ご利用明細書」を忘れずに保管しておきましょう。
受験票を受け取る
受験票はハガキ形式で、9月下旬ごろに到着します。
氏名、受験会場を確認し、不備があれば早急に問い合わせ窓口まで連絡しましょう。
受験票は試験当日必ず持参しなければならないものなので、到着次第大切に保管しましょう。
日本語教育能力検定試験に合格するための勉強方法

日本語教育能力検定試験の勉強において重要なのは、基礎的知識の網羅的学習と、知識を活用したアウトプット学習です。
まずは、テキストに書かれている基礎的内容を満遍なく頭に入れましょう。
ポイントは「広く、浅く」です。
ある程度知識が頭に入ったと感じたら、次は過去問教材を使用し、知識のアウトプットを行います。
過去問を解いて不明な点があればその都度テキストで確認し、
とくに苦手な分野や項目についてはテキストや用語集を使い反復学習を徹底しましょう。
網羅的に知識を定着させ、さらに知識を活用した演習を行い、インプットとアウトプットを繰り返し行うことで、
合格に必要な知識が効率よく定着し、問題を解くのに必要な応用力も身につきます。
日本語教育能力検定試験は独学で合格できる?
独学で日本語教育能力検定試験に合格することは可能です。
しかし、独学の場合には、自分で学習を計画的に進めたり、予習復習をベースとする学習サイクルを維持したりする力が必要です。
学習のペースやスケジュールを自分で管理するのは難しいという場合には、
日本語教師養成講座に通ったり、検定対策講座を受講したりすることを検討するとよいでしょう。
養成講座や検定対策講座は通学形式のものだけでなくe-ラーニング形式のものもありますので、
自分のライフスタイルに合わせた形式のものを選ぶことが大切です。
日本語教員国家試験対策コース | ルネサンス日本語学院 日本語教師養成講座
日本語教師とはどのような仕事か、日本語教師になるための勉強方法、日本語教師として仕事に就くには・・・など、
疑問や不安のある方は、まずは受講相談/資料請求・お電話で私たちルネサンス日本語学院にお問い合わせください。
日本語教育の現状や日本語教師の資格、検定試験など、
日本語教育に関する概要とルネサンス日本語学院の養成講座についてご案内いたします。
日本語教育能力検定試験は誰でも受けられる
日本語教育能力検定試験は、必要な受験資格がなく、誰でも簡単に受験できる検定資格です。
国家資格とは違いますが、自らの日本語教育能力と知識が一定の基準に達していることを客観的に示せることがメリットです。
日本語教員試験を受ける前に力試しとして受験を検討するのはいかがでしょうか。
日本語教師養成講座ならルネサンス日本語学院におまかせください!
日本語教師の国家資格「登録日本語教員」になるためのサポートをおこなっています。
日本語教師に興味を持った方は、ぜひお気軽にお問合せください。
<関連記事>登録日本語教員とは 国家資格化に伴いどう変わる?
<関連記事>日本語教育能力検定試験に合格するために必要な勉強時間
<関連記事>日本語教育能力検定試験はどの会場で実施されるのか?
<関連記事>日本語教育能力検定試験はどんな試験?合格ラインや勉強方法を徹底解説
この記事の監修者

ルネサンス日本語学院 日本語教師養成講座講師
《資格》日本語教師養成課程修了・日本語教育能力検定試験合格
《経歴》日本語教師養成講座を修了後、約30年に渡り、大使館、留学生、インターナショナルスクール、企業などで日本語教育に従事。また、(社)国際日本語普及協会の「地域日本語教育コーディネーター研修」修了後は、地域の日本語教育、ボランティア支援や教育委員会日本語研修プログラム、NHK文化センター、一部上場企業などへの日本語教育コーディネイトや日本語教師養成に携わり、日本語教育総合支援など多方面で活躍中。
《専門分野》就労者・生活者・年少者に対する日本語教育。
《監修者からのコメント》
日本語教師の勉強は、「知識」だけでも、「技術」だけでもだめです。 両方揃って初めて「学習者」という同乗者が安心して授業を受けられます。単なる知識の講座ではなく、皆さんより少し先を歩く私たち現役日本語教師が考え、悩み、苦労してたどり着いた答えを多く取り入れた「現場目線」を意識しています。
私自身、国語教師を目指し、日本語の文法にも自信があったにもかかわらず、「こんにちは。」の使い方を外国人に教えられなかった…というショックから、「日本語」に興味を持ち、日本語教師になりました。日本語教育業界は、わかりやすそうでわかりにくいですから、この業界の専門知識のある人に相談することがおすすめです。ぜひお気軽にお問い合わせください。
- 日本語教師になる第一歩はこちら 資料請求
- 専任の担当者が回答します 個別相談・お問い合わせ
電話でのお問い合わせ・ご相談はこちら
※学院生の皆様はマイページ
「事務局への質問」から
お問い合わせください。
平日・土曜 9:30-18:00


