日本語教師養成コラム
【最新】日本語教員試験とは?試験内容や合格基準を解説
公開日:2025.01.28 更新日:2025.06.13

監修者情報
ルネサンス日本語学院 日本語教師養成講座講師

2024年4月から、これまで民間資格だった日本語教師が国家資格となり、
国家試験となる「日本語教員試験」が2024年11月17日に実施されました。
"認定日本語教育機関"で働く際には、日本語教師を志している方や現職の日本語教師の方も、
この試験に合格して"登録日本語教員"となることが必須です。
そこで本記事では、登録日本語教員を目指す方が受験する日本語教員試験について解説します。
日本語のプロとして、幅広く活躍したい方はご一読ください。
電話でのお問い合わせ・ご相談はこちら
日本語教員試験とは

日本語教員試験とは、認定日本語教育機関で働く日本語の教師として、
ふさわしい知識や技能を備えているか否かを測る資格試験のことです。
そもそも認定日本語教育機関とは何かというと、
「適性かつ確実な日本語教育が実施できる」と文部科学大臣認定を受けた日本語教育機関のことを指します。
具体的には、現在の日本語学校や留学生別科などが想定されています。
ここで日本語を教えることができるのが、登録日本語教員です。
日本語教員試験は、"基礎試験"と"応用試験(聴解・読解)"の、2部構成となっています。
これらの試験に合格したあと、"実践研修"を経て、晴れて登録日本語教員として認定されるのです。
さて、ここまでの内容を見ると、「国家試験となると難易度が高そうだし、受験資格も厳しいんじゃないの?」
と思われる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし日本語教員試験は、年齢・学歴・国籍を問わず受験できます。
つまり、これから登録日本語教員として認定日本語教育機関で働きたい方なら、
誰にでもチャンスがあるということです。
参照元:文部科学省 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律の概要
登録日本語教員になるための資格取得ルート

日本語教員試験は、登録日本語教員を志す方の状況に応じて、主に2つのルートから選択できます。
以下の内容を参考に、ご自身がどのルートに該当するのかを確認してみてください。
なお、現職者が登録日本語教員になるためのルートは次項で解説します。
<関連記事>【2024年最新版】国家資格「登録日本語教員」になるには?
養成機関ルート
"養成機関ルート"とは、文部科学省に認定された日本語の養成機関で課程を修了することで、
基礎試験が免除される道筋のことです。
では、さっそく養成機関ルートの概要を見ていきましょう。
対象者が通う養成機関によって、以下で示す2つのコースが用意されています。
養成機関ルート
| 対象者 | 登録実践研修機関と登録日本語教員養成機関の登録を受けた機関の両方で課程を修了する方 ・大学等(26単位~) ・専門学校等(420単位時間~) | 登録日本語教員養成機関の登録を受けた機関のみで課程を修了する方 ・大学等(25単位~) ・専門学校等(375単位時間~) |
| 基礎試験 | 免除 | 免除 |
| 応用試験 | 受験が必要 | 受験が必要 |
| 実践研修 | 養成課程と一体的に実施 | 別途、登録実践研修機関にて実施 |
上記の表からもわかるように、養成機関ルートでは基礎試験は免除されますが、応用試験は必須です。
そのうえで、研修機関での実践研修を受けずに養成機関のみで課程を修了した方は、別途実践研修を受ける必要があります。
なお、登録日本語教員養成機関については、文化庁のホームページで対象となる機関の一覧が公表されています。
参照元:「日本語教育機関の告示基準」(平成28年7月22日出入国在留管理庁策定)第1条第1項第13号ニに規定する
日本語教員の要件として適当と認められる研修について届出を受理された日本語教員養成研修実施機関・団体
試験ルート
特定の養成機関で学習するのではなく、ご自身の力のみで知識を蓄えて受験したい方に向いているのが、
"試験ルート"です。
試験ルートでは免除される項目はないので、独力で勉強したのちに基礎試験と応用試験を通過して、
登録実践研修機関で実習を修了する必要があります。
<関連記事>【2025年最新版】日本語教師になるには?仕事内容や、向いている人について解説!
現職者が登録日本語教員資格を取得するには

現職者が日本語教員試験を通過して登録日本語教員となるためには、"経過措置ルート"を選択します。
このルートはご本人が修了した課程や、これまでの日本語教師としての経験によって、以下の6つのルートに分けられています。
経過措置ルートの対象者
| ルート | 対象者 |
| 経過措置Cルート | 現職者に限らず、必須の50項目を実施していることが確認できた現行告示基準教員要件に該当する養成課程等を修了し、学士以上の学位を有する方 |
| 経過措置D-1ルート | 現職者のうち、必須の50項目対応前の課程を修了した方で、5区分の教育内容を実施していることが確認できた現行告示基準教員要件に該当する養成課程等を修了し、学士以上の学位を有する方 |
| 経過措置D-2ルート | 現職者のうち、必須の50項目対応前の課程を修了した方で、現行告示基準教員要件に該当する養成課程等を修了し、学士以上の学位を有する方 |
| 経過措置E-1ルート | 現職者のうち、昭和62年4月1日~平成15年3月31日の間に実施された日本語教育能力検定試験(公益財団法人日本国際教育支援協会)に合格した方 |
| 経過措置E-2ルート | 現職者のうち、平成15年4月1日~令和6年3月31日の間 に実施された日本語教育能力検定試験(公益財団法人日本国際教育支援協会)に合格した方 |
| 経過措置Fルート | 上記以外の現職者 |
上記の経過措置ルートなら、一部の試験項目が免除されるため、
日本語教師としての経験を活かしつつ効率的に試験合格を目指せるのです。
しかし、すべての方が一律で同じ試験が免除されるわけではなく、ルートによって免除される試験・研修は異なります。
また、場合によっては別途講習の受講が求められます。
経過措置ルートごとに免除される試験・研修と、必要な試験・講習は以下の通りです。
経過措置ルートごとに免除される試験・研修と必要な試験・講習
| ルート | 免除される試験・研修 | 必要な試験・講習 |
| 経過措置Cルート | ・基礎試験 ・実践研修 | ・応用試験 |
| 経過措置D-1ルート | ・基礎試験 ・実践研修 | ・講習Ⅱ ・応用試験 |
| 経過措置D-2ルート | ・基礎試験 ・実践研修 | ・講習Ⅰ ・講習Ⅱ ・応用試験 |
| 経過措置E-1ルート | ・基礎試験 ・応用試験 ・実践研修 | ・講習Ⅰ ・講習Ⅱ |
| 経過措置E-2ルート | ・基礎試験 ・応用試験 ・実践研修 | ・講習Ⅱ |
| 経過措置Fルート | ・実践研修 | ・基礎試験 ・応用試験 |
上記の表にある講習Ⅰでは90分×5コマ程度、講習Ⅱは90分×10コマ程度の講習が実施され、
講習後は修了試験に合格する必要があります。
その際に発行される修了証は日本語教員試験の出願時に提出するため、必ず出願前に講習を受講してください。
実施方法に関しては、受講機会確保の観点から、自宅でも受けられるオンデマンド方式が採用されています。
なお、試験免除に必要な書類については後述します。
現職者でも登録日本語教員資格は取得したほうがよい?

現職の日本語教師であっても、認定日本語教育機関で働くためには登録日本語教員資格が必須なので、
将来的な選択肢を狭めたくないのであれば受験することを推奨します。
2024年11月時点で、経過措置ルートが適用されるのは原則2029年3月31日までとされており、
もしこの期間を過ぎた場合は養成ルートか試験ルートでしか資格を取得できなくなります。
受験するタイミングは個人の判断に委ねられますが、早いに越したことはありません。
<関連記事>登録日本語教員の制度はいつから?資格の詳細や必要性を解説
日本語教員試験の概要

ここからは、いよいよ日本語教員試験の概要に触れていきます。
まずは大枠を捉えていただくために、以下の表をご覧ください。
日本語教員試験の概要
| 基礎試験 | 応用試験 | |
| 試験時間 | 120分 | 聴解:50分 読解:100分 |
| 出題数 | 100問 | 聴解:50問 読解:60問 |
| 出題形式 | 選択式 | |
| 配点 | 1問1点(計100点) | 1問1点(計110点) |
| 合格基準 | 詳細は後述 | |
| 受験料 | 通常:1万8,900円 基礎試験免除:1万7,300円 基礎試験・応用試験免除(免許資格の確認手数料):5,900円 | |
上記の表を踏まえたうえで、一つひとつの項目をさらに詳しく見ていきましょう。
参照元:文部科学省 令和 6 年度 日本語教員試験 試験案内
<関連記事>日本語教師資格の難易度は?国家資格化による変更点
日本語教員試験の試験内容
基礎試験の内容を確認するうえでまず押さえておきたいのは、養成機関でも学ぶこととなる、
日本語教師養成課程において必須の教育内容50項目です。
これは、日本語教師として各分野で活躍するにあたっての資質や能力を育むための教育項目として、
文化庁が定めたものです。
日本語教員試験では、この50項目をもとに5つの区分に分けて出題されます。
では、日本語教員試験の基礎試験の出題範囲を詳しく見ていきましょう。
日本語教員試験の出題範囲(基礎試験)
| 全体項目 | 一般目標 | 必須の教育内容50項目 | おおまかな出題割合 |
| 1.社会・文化・地域 | ①世界と日本 | <1>世界と日本の社会と文化 | 約1~2割 |
| ②異文化接触 | <2>日本の在留外国人施策 <3>多文化共生(地域社会における共生 | ||
| ③日本語教育の歴史と現状 | <4>日本語教育史 <5>言語政策 <6>日本語の試験 <7>世界と日本の日本語教育事情 | ||
| 2.言語と社会 | ④言語と社会の関係 | <8>社会言語学 <9>言語政策と「ことば」 | 約1割 |
| ⑤言語使用と社会 | <10>コミュニケーションストラテジー <11>待遇・敬意表現 <12>言語・非言語行動 | ||
| ⑥異文化コミュニケーションと社会 | <13>多文化・多言語主義 | ||
| 3.言語と心理 | ⑦言語理解の過程 | <14>談話理解 <15>言語学習 | 約1割 |
| ⑧言語習得・発達 | <16>習得過程(第一言語・第二言語) <17>学習ストラテジー | ||
| ⑨異文化理解と心理 | <18>異文化受容・適応 <19>日本語の学習・教育の情意的側面 | ||
| 4.言語と教育 | ⑩言語教育法・実習 | <20>日本語教師の資質・能力 <21>日本語教育プログラムの理解と実践 <22>教室・言語環境の設定 <23>コースデザイン <24>教授法 <25>教材分析・作成・開発 <26>評価法 <27>授業計画 <29>中間言語分析 <30>授業分析・自己点検能力 <31>目的・対象別日本語教育法 | 約3~4割 |
| ⑪異文化間教育とコミュニケーション教育 | <32>異文化間教育 <33>異文化コミュニケーション <34>コミュニケーション教育 | ||
| ⑫言語教育と情報 | <35>日本語教育と ICT <36>著作権 | ||
| 5.言語 | ⑬言語の構造一般 | <37>一般言語学 <38>対照言語学 | 約3割 |
| ⑭日本語の構造 | <39>日本語教育のための日本語分析 <40>日本語教育のための音韻・音声体系 <41>日本語教育のための文字と表記 <42>日本語教育のための形態・語彙体系 <43>日本語教育のための文法体系 <44>日本語教育のための意味体系 <45>日本語教育のための語用論的規範 | ||
| ⑮コミュニケーション能力 | <46>受容・理解能力 <47>言語運用能力 <48>社会文化能力 <49>対人関係能力 <50>異文化調整能力 |
上記に応用試験の出題割合が記載されていないのは、区分を横断した出題がなされるためです。
応用試験では、基礎的な知識や技能を活用した問題解決能力を測るので、
一つの区分に限らず、教育実践に関連付けられた問題が出されます。
なお、<28>は"教育実習"となっており、本試験においては出題の対象ではありません。
日本語教員試験の試験時間と出題数
次に試験時間と出題数についてですが、基礎試験の場合は120分という限られた時間内で、
100問の出題に解答する必要があります。
各問題の配点は1点なので、満点を目指すなら1問あたり約72秒で解かなければならない計算になります。
また、応用試験は音声で出題される"聴解"と、文章問題である"読解"の2部構成です。
聴解は50分で50問出題されるので1問あたり約60秒、読解の場合は100分で60問出題されるため
1問あたり約100秒で解かなければなりません。
これを踏まえると、解答には相当なスピード感が求められることがわかります。
日本語教員試験の合格基準
基礎試験の合格基準は、必須の教育内容50項目で構成された5つの区分において、
それぞれ6割の得点があり、なおかつ全体で8割の正答率があることです。
一方の応用試験では、全体で6割の正答率が求められます。
なお、いずれの試験も年度ごとの試験の難易度を考慮したうえで、合格基準が見直される可能性があります。
日本語教員試験の時間割
日本語教員試験の概要とあわせて、試験当日の時間割についてもお知らせします。
ここで紹介するのは、2024年11月の第1回日本語教員試験の時間割です。
2024年11月の第1回日本語教員試験の時間割
| 着席時刻 | 所要時間 | |
| 開場 | - | 9:00~9:40 |
| 基礎試験 | 9:40 | 10:00~12:00(120分) |
| 昼休憩 | - | 12:00~13:00 |
| 応用試験(聴解) | 13:00 | 13:20~14:10(50分) |
| 休憩 | - | 14:10~14:30 |
| 応用試験(読解) | 14:00 | 14:50~16:30(100分) |
どのような試験においても言えることですが、
決められた時間に席に着いていない場合は受験できなくなる可能性があるので注意してください。
電話でのお問い合わせ・ご相談はこちら
日本語教員試験の試験会場
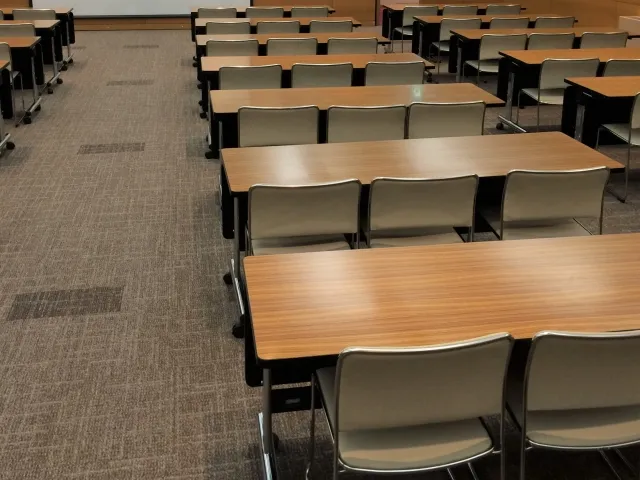
日本語教員試験の概要とあわせて、試験会場についても把握しておきましょう。
ここでは、2024年11月実施の第1回日本語教員試験のときの会場をお伝えします。
第1回日本語教員試験の会場
| エリア | 会場 |
| 北海道 | TKP札幌カンファレンスセンター |
| 東北 | TKPガーデンシティ PREMIUM 仙台西口 |
| 関東 | 駒澤大学(駒沢キャンパス) |
| TOC五反田 | |
| TKPガーデンシティ PREMIUM 品川高輪口 | |
| TKP新橋カンファレンスセンター | |
| 中部 | 名城大学(天白キャンパス) |
| 近畿 | 大阪公立大学(中百舌鳥キャンパス) |
| 中四国 | TKPガーデンシティ PREMIUM 広島駅前 |
| 九州 | 九州大学(伊都キャンパス) |
| 沖縄 | 沖縄コンベンションセンター |
上記の試験会場は施設の都合で変更される可能性があるので、受験に際しては受験票に記載された会場の確認が必須です。
基礎試験のおすすめの試験対策
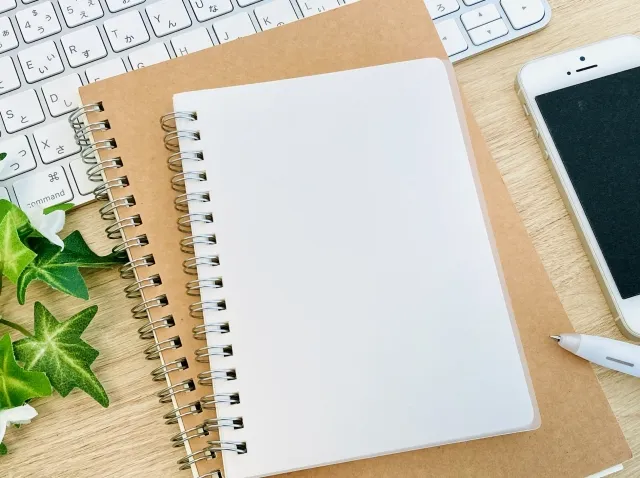
さて、日本語教員試験の概要を把握したことで、より現実味が増してきたのではないでしょうか。
そうなると、次に気になるのは試験への対策方法でしょう。
ここからは、文部科学省が公開しているサンプル問題をもとに、基礎試験の対策方法を紹介します。
用語集の内容を押さえる
まずは、養成機関から渡される用語集の内容を網羅的に頭に入れておきましょう。
独学の場合は市販のものでも構わないので、きちんと読み込んで、
何を質問されてもある程度は答えられるほどに理解を深めておきたいところです。
基礎試験は各区分で6割の正答率が必要なうえ、全体の8割の得点が求められます。
そのため、いわゆる"ヤマを張る"という学習方法は適していません。
一朝一夕で合格できる試験ではないことを念頭に置いて、コツコツと満遍なく学習を進めてください。
関連資料に目を通す
用語集とあわせて、日本語教育の関連資料にも目を通しておくことをおすすめします。
なかでも、2021年に文化庁から公表された"日本語教育の参照枠"は必読です。
日本語教育の参照枠とは、日本語教育に携わるすべての方が参照できる、
日本語の学習・教授・評価のための包括的なフレームワークのことです。
同じく文化庁から公表されている、2023年12月に実施された日本語教員試験の試行試験の問題のなかには、
この枠組みの理念や考え方をもとにした設問も見受けられました。
日本語教育の参照枠は確実に押さえたうえで、そのほかの関連資料にもできるだけ多く触れておきましょう。
参照元:文化庁 「日本語教育の参照枠」の概要
参照元:文化庁 日本語教員試験試行試験 結果の概要
応用試験(聴解)のおすすめの試験対策

応用試験で試されるのは、現場対応能力や問題解決能力です。
この試験では、音声による出題と文章問題の2部構成となっており、
基礎問題とは出題形式が若干異なります。
まずは、音声によって出題される"聴解試験"の対策方法から見ていきましょう。
聴解試験は、実際に教室で交わされる教師と日本語学習者との会話を用いて、
より教育実践に即した問題が出される試験です。
これを踏まえたうえで、以下の対策を講じてください。
なお、基礎試験と同様に応用試験の対策方法においても、サンプル問題からイメージをつかんだうえで解説していきます。
出題パターンを把握する
日本語教員試験は2024年から始まったばかりの試験ですので、
過去問がほとんど出回っていないのが現状です。
「それならどうやって勉強したらいいの?」と思われるかもしれませんが、
以前から実施されている"日本語教育能力検定試験"の過去問集を活用してみてください。
なぜなら、日本語教員試験の聴解試験は、日本語教育能力検定試験の問題を踏襲した内容になっているからです。
何度も過去問を解いて複数の出題パターンを把握しておけば、
いざ試験本番を迎えた際に慌てず冷静に解答できることでしょう。
聴解試験では、"高低のアクセント"や"文末のイントネーション"などの問題が出されるといわれています。
ひたすら過去問の音源を聞いて、アクセントがわからない場合は声に出してみるとニュアンスをつかめるかもしれません。
受験のテクニックを身につける
細かいことですが、ある種の受験テクニックを身につけておくのも一案です。
先述のように、聴解問題は50分で50問出題されるため、1問あたり約60秒しか時間を充てられません。
たとえば少しでも早く問題が解けたら、すぐに次の問題や選択肢を読んでおくことで、
ある程度の時間の余裕が生まれます。
また、5問ごとに小休憩が設けられているため、そのあいだに次の問題に備えておくのも有効でしょう。
このようなテクニックを駆使すれば、どれだけ聴解試験の進行が速くても
一つひとつの問題にきちんと対応できるようになり、心にゆとりをもって取り組めるはずです。
リスニングに慣れる
聴解試験においては、リスニングに慣れておくことも重要です。
実際の試験を想定しながら過去問や模擬試験を何度も繰り返せば、
本番でもリラックスした状態を保ちながら解答できるようになるかもしれません。
また、試験当日は普段と異なる環境で問題を解くことになります。
50分間にわたる聴解試験で集中力を切らさないために、繰り返し対策することで
最後までやり切る精神力を鍛えておくことも大切です。
応用試験(読解)のおすすめの試験対策
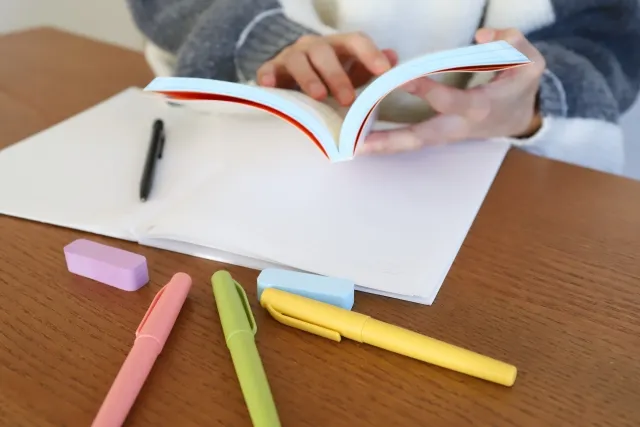
続いて、応用試験における"読解試験"の対策方法についてもお伝えします。
読解試験では長文問題が出題され、4つの選択肢から解答を選ぶ形式がとられており、言葉の通り読解力が試されます。
以下で紹介する対策を講じて、万全の体制で試験に臨みましょう。
問題集をひたすら解く
読解試験の対策方法としては、とにかく多くの問題集を解くことが有効です。
ただし応用試験では、基礎的な知識と技能を活用した実践的な問題解決能力を図るため、
"教育実践"と関連付けられた問題が出されるといわれています。
教室内で交わされる日本語学習者と教師とのやり取りや、教師としての在り方などが出題の中心になると予想されます。
そのため、日本語教育の現場に立って実際に授業を行っている現職者のほうが有利といえるかもしれません。
とはいえ、まだ日本語を教えたことがない方でも、
問題集にある教育実践に関わる設問を解きつづければ、現職者との差を少なからず縮められる可能性があります。
積極的に挑戦して、日本語学習の授業に関わる知識を蓄積しましょう。
関連資料を押さえる
読解試験でも、日本語教育の関連資料はチェックしておくに越したことはありません。
先述した日本語教育の参照枠をはじめ、さまざまな関連資料に目を通しておけば、
現場の教育活動の基盤を理解できます。
基礎試験と並行して、教育実践に関わる内容も頭で整理したうえで、きちんとアウトプットできるよう学習を進めましょう。
簡単なことではありませんが、日本語教育の現場に立つご自身の姿をイメージしながら、前向きに取り組んでみてください。
日本語教員試験の申し込み方法

ここからは、日本語教員試験への申し込み方法について、順を追ってお伝えします。
受験者の状況や経験によって必要書類が異なるので、
以下の内容をご確認いただき、ご自身と照らし合わせたうえで、漏れのないよう準備してください。
事前に用意するもの
日本語教員試験への申し込みにあたって事前に用意するものは、
"試験免除に必要な書類"と"顔写真データ"です。
この試験免除に必要な書類は、現職者向けの6つの経過措置ルートごとに異なります。
いくつものルートが出てきて少々混乱するかもしれませんが、一つひとつ慎重に見ていけば、
ご自身が該当するルートと必要書類が明確になるはずです。
以下に養成機関ルートと試験ルートも含めた、
計8つのルートごとに必要な書類をまとめましたので、ご参照ください。
ルートごとの必要書類一覧
| ルート | 必要書類 |
| 養成機関ルート | ・登録日本語教員養成機関の養成課程修了証書(写し) |
| 試験ルート | - |
| 経過措置Cルート | ・必須の教育内容 50 項目に対応した日本語教員養成課程等の修了の証明書(写し) ・学士、修士または博士の学位の証明書 |
| 経過措置D-1ルート | ・平成 12 年報告に対応した日本語教員養成課程等の修了の証明書(写し) ・学士、修士または博士の学位の証明書(写し) ・講習Ⅱの修了証(写し) ・日本語教育機関の在職証明書(写し) |
| 経過措置D-2ルート | ・法務省告示基準教員要件に該当する日本語教員養成課程等の修了の証明書(写し) ・学士、修士または博士の学位の証明書(写し) ・講習Ⅰおよび講習Ⅱの修了証(写し) ・日本語教育機関の在職証明書(写し) |
| 経過措置E-1ルート | ・日本語教育能力検定試験合格証書(昭和62年度~平成14年度)(写し) ・講習Ⅰおよび講習Ⅱの修了証(写し) ・日本語教育機関の在職証明書(写し) |
| 経過措置E-2ルート | ・日本語教育能力検定試験合格証書(平成15年度~令和5年度)(写し) ・講習Ⅱの修了証(写し) ・日本語教育機関の在職証明書(写し) |
| 経過措置Fルート | ・日本語教育機関の在職証明書(写し) |
上記の表にある"講習の修了証"とは、先述した講習Ⅰか講習Ⅱ、あるいはその両方を受講したという証のことです。
なお、顔写真データは6か月以内に撮影したもので、データ形式はJPEG、データサイズは10MB以下と規定されています。
その際、カラー・白黒は問いません。
出願の流れ
次は、出願の流れをお伝えします。 日本語教員試験の出願は、以下の手順で進めてください。
【日本語教員試験の出願の手順】
1.アカウント作成
2.マイページ作成
3.受験者登録
4.受験科目申請・免除申請書類のアップロード
5.受験料の支払い
まずは、文部科学省の日本語教員試験のページから、願書申請サイトにアクセスします。
そこでアカウントを作成し、登録したメールアドレスに送られてくるURLからマイページ作成に移行してください。
作成後はマイページのURLが送られてくるので、
ログインして受験者情報の入力と顔写真データをアップロードしましょう。
このときに、資格取得ルートの入力と、免除申請書類のアップロードもあわせて行います。
以上で、日本語教員試験の出願手続きは完了です。
参照元:文部科学省 日本語教員試験に関すること 願書申請操作マニュアル.pdf
受験料の支払い方法
手続きが終了したあとは、受験料の支払いに移ります。
日本語教員試験の受験料は、収入印紙で納付します。
送付される受験案内の中にある"収入印紙提出用台紙"に、受験料ぶんの収入印紙を貼り付けて郵送してください。
なお、この台紙はオンラインで出願する際にもダウンロードできます。
受験票について
受験票は、試験機関から送られてくるのではなく、
オンライン出願サイトのマイページ上にPDF形式で発行されます。
ご自身で受験票をダウンロードしたうえで、A4サイズの用紙に印刷したものを試験会場に持参する必要があります。
受験票はダウンロードした画像を提示するだけでは無効となるので、
必ず用紙に印刷しておいてください。
もし受験票を忘れた場合は、本人確認のために身分証明書の提示が求められます。
日本語教員試験は、認定日本語教育機関で働くうえで必須な登録日本語教員資格を取得するための試験

今回は、日本語教員試験の概要についてお伝えしました。
日本語教員試験は、認定日本語教育機関で働くうえで不可欠な登録日本語教員資格を取得するための試験です。
この試験では受験者ごとにルートが分かれていますので、
ご自身に当てはまるルートを慎重に見極めて、必要な対策を講じたうえで試験に臨みましょう。
日本語教師養成講座ならルネサンス日本語学院にお任せください。
2025年からは「登録日本語教員養成・実践研修コース」を開講しています。
eラーニングにも対応しており、学歴・国籍・年齢不問で学習できる講座となっていますのでぜひお問い合わせください。
この記事の監修者

ルネサンス日本語学院 日本語教師養成講座講師
《資格》日本語教師養成課程修了・日本語教育能力検定試験合格
《経歴》日本語教師養成講座を修了後、約30年に渡り、大使館、留学生、インターナショナルスクール、企業などで日本語教育に従事。また、(社)国際日本語普及協会の「地域日本語教育コーディネーター研修」修了後は、地域の日本語教育、ボランティア支援や教育委員会日本語研修プログラム、NHK文化センター、一部上場企業などへの日本語教育コーディネイトや日本語教師養成に携わり、日本語教育総合支援など多方面で活躍中。
《専門分野》就労者・生活者・年少者に対する日本語教育。
《監修者からのコメント》
日本語教師の勉強は、「知識」だけでも、「技術」だけでもだめです。 両方揃って初めて「学習者」という同乗者が安心して授業を受けられます。単なる知識の講座ではなく、皆さんより少し先を歩く私たち現役日本語教師が考え、悩み、苦労してたどり着いた答えを多く取り入れた「現場目線」を意識しています。
私自身、国語教師を目指し、日本語の文法にも自信があったにもかかわらず、「こんにちは。」の使い方を外国人に教えられなかった…というショックから、「日本語」に興味を持ち、日本語教師になりました。日本語教育業界は、わかりやすそうでわかりにくいですから、この業界の専門知識のある人に相談することがおすすめです。ぜひお気軽にお問い合わせください。
- 日本語教師になる第一歩はこちら 資料請求
- 専任の担当者が回答します 個別相談・お問い合わせ
電話でのお問い合わせ・ご相談はこちら
※学院生の皆様はマイページ
「事務局への質問」から
お問い合わせください。
平日・土曜 9:30-18:00



