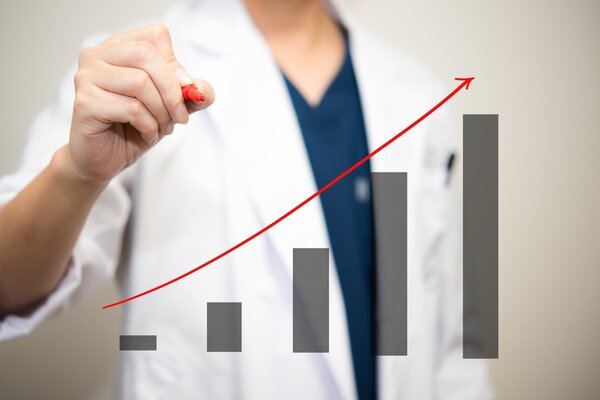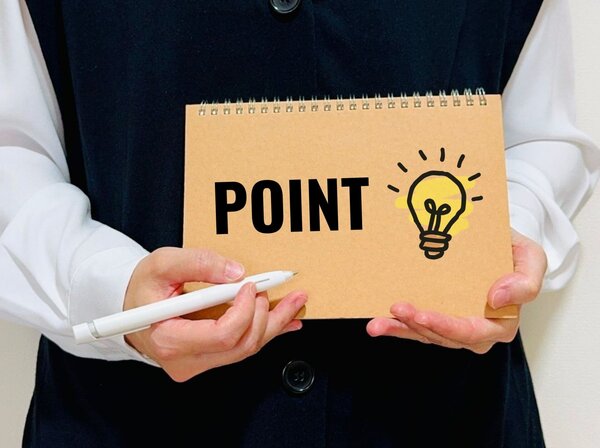日本語教師養成コラム
外国人労働者の受け入れの現状と雇用するメリット・デメリット
公開日:2025.07.28 更新日:2025.08.05

監修者情報
ルネサンス日本語学院 日本語教師養成講座講師
少子高齢化による労働力不足が深刻化している昨今、外国人労働者の雇用が欠かせません。 採用担当者においては、自社の労働力不足を補填する際の参考として、外国人労働者の受け入れの現状を把握しておきたいところです。
本記事では、外国人労働者の推移を解説したうえで、雇用するメリットや押さえておきたいポイントを紹介します。 未曾有の人材不足を切り抜けるために、外国人労働者を採用したい方は、ぜひご一読ください。
外国人労働者の推移
2008年以降、外国人労働者は増加傾向にありますが、特に2014年から2024年の10年間で急増しています。 厚生労働省が提示する"在留資格別外国人労働者数の推移"によると、2014年の外国人労働者は78.8万人であるのに対して、2024年では230.3万人と約3倍に増えているのです。
外国人労働者の数は、2007年に外国人雇用状況の届出が義務化されて以来、2023年に初めて200万人を超えました。 なお、"国籍別外国人労働者の割合"を見ると、2024年時点でもっとも多いのはベトナム人であり、全体の24.8%を占めていることがわかります。
次いで17.8%の中国、10.7%のフィリピンの順に多く、全体の半分以上がアジア地域からの外国人労働者であるといえます。
参照元:厚生労働省「「外国人雇用状況」の届出状況まとめ【本文】(令和6年10月末時点)p4、p5、p6」
外国人労働者が増えている理由
日本で働く外国人労働者が増えているのはなぜでしょうか。 その背景には、日本の労働人口における問題と、それに伴う外国人労働者の需要の高まりがあると考えられます。
以下で、外国人労働者が増えている理由を、掘り下げて見ていきましょう。
人手不足が深刻化しているため
外国人労働者が増えている理由として、まず挙げられるのは、日本の労働力不足の深刻化です。 内閣府の資料によると、日本社会の生産活動の中心を担う15~64歳の方の人口は1995年の8,716万人をピークに減少傾向にあり、2023年10月時点で7,395万人になりました。
これは、日本の総人口の59.5%にあたります。 このように日本の労働人口は年々減少しているため、政府が外国人労働者を積極的に受け入れる動きを見せているのです。
手厚い支援があるため
日本の労働力減少に伴い、日本政府が日本で求職する外国人と、外国人材の採用を検討している企業を支援していることも、外国人労働者が増えている理由の一つです。
たとえば、外国人求職者のために、ハローワークへの通訳サービスや外国人出張行政コーナーの設置のほか、外国人就労・定着支援研修などが提供されています。
この研修の主な目的は、日本の職場の習慣や労働関係法令などに関する知識の習得、またコミュニケーション能力の向上です。 また、一方、外国人労働者を雇用した企業は、補助金または助成金を受け取れます。
補助金・助成金には、人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)、人材開発支援助成金(特定訓練コース)、雇用調整助成金などさまざまな種類があります。
このように、外国人労働者と企業に対する手厚いサポート体制も、外国人労働者が増加する一因となっているのです。
企業が積極的に外国人労働者を採用しているため
海外で事業を展開している企業や、将来的に海外市場への進出を見据えている企業は、進出先の国の言語を母語とする外国人労働者を積極的に採用する傾向にあります。
さらに近年は日本国内でもインバウンド需要が高まっているため、多言語に対応した人材が求められるようになりました。
このようなグローバル化の波に後押しされ、外国人労働者の雇用を前向きに検討する企業が増加しています。
日本での労働を希望する外国人が増えているため
日本国内の外国人労働者の需要の高まりとともに、日本での就労を希望する外国人の数も増えています。
母国での就職が難しい、また給料が低くて生活が厳しいなどの理由から、母国よりも就労条件が良い日本企業への就業を選択する外国人が多いようです。
また、日本は治安が良く、住みやすい国として知られているうえに、アニメやゲームといったポップカルチャーが世界的に人気を博しています。
こうした日本ならではの特徴が外国人の目に魅力的に映り、「日本で働きたい!」と決意するケースもみられます。
外国人労働者を受け入れるメリット
今後も増加が予想される外国人労働者を受け入れるにあたって、企業はどのようなメリットを得られるのでしょうか。
企業の発展に関連する、主なメリットを3つ紹介します。
メリット①自社のグローバル化が進む
外国人労働者の受け入れで得られる大きなメリットは、自社のグローバル化の進展です。 さまざまな外国人労働者を受け入れることで、ビジネスにおける対応言語が多様化します。
これによって、市場開拓が活発化する可能性があり、グローバルな事業展開が期待できるといえるでしょう。
メリット②自社の従業員に良い影響を与えられる
外国人労働者の受け入れが、自社の従業員にとって良い刺激となる点もメリットの一つです。 外国人労働者のなかには、母語以外にも複数の言語に対応できる方もいます。
海外進出を視野に入れている企業であれば、外国人労働者を雇用して社内の公用語を外国語にすることによって、社員の言語能力の底上げにつながります。
また、社員の言語能力が向上すれば、販路の拡大が期待でき、海外進出の足掛かりになる可能性もあるのです。 さらに、他国の文化や技術を取り入れると、新たなアイディアを生み出せるかもしれません。
外国人労働者とともに働くことで得られる学びや気づきが、従業員を成長させるでしょう。
メリット③採用コストを抑えることができる
介護職や建設業、また飲食業などの人手不足に陥りやすい職種では、外国人労働者の受け入れによって、採用コストの削減につながることがあります。
人手不足が続いていると、長期間にわたって募集や選考、また採用を繰り返す必要があり、膨大な採用コストがかかります。
そこで、外国人も採用対象に含んで求職者の数が増えれば、採用サイクルを短縮して求人広告費や採用担当者の人件費などを抑えられるというわけです。
また外国人を採用した際に利用できる助成金もあるため、賢く活用することで採用コストを補うことができます。
外国人労働者を受け入れるデメリット
外国人労働者の受け入れには自社のグローバル化の促進や採用コストの削減といったメリットがありますが、同時にデメリットも存在します。
この項では、具体的にどのようなデメリットがあるのかを、見ていきましょう。
デメリット①文化や習慣に違いがある
外国人労働者の受け入れによって、文化や習慣の違いによるトラブルが起こりうる点はデメリットといえます。 国によって価値観やマナーが異なるため、日本では当たり前のルールが、外国人労働者には通用しないといったケースも珍しくありません。
このような認識の相違が業務にも影響する可能性があり、意見の食い違いからトラブルに発展することもあるのです。
外国人労働者を採用する際には、お互いの文化の違いを正しく認識したうえで、どちらか一方の価値観を押し付けずに、尊重し合うことが重要です。
デメリット②コミュニケーションの難しさを感じることがある
コミュニケーションの難しさも、外国人労働者を受け入れる際のデメリットといえます。 採用する外国人労働者が、日本語を必ずしも流暢に話せるとは限りません。
外国人労働者の日本語レベルによっては、コミュニケーションを円滑に図れず、業務に支障をきたす場合もあります。 このような事態を避けるためには、外国人労働者の日本語能力を伸ばすことが不可欠です。
企業においては、社内で日本語の研修を行う、または外部の講師を招いて講習を行うといった、学習のサポートを実施するのがおすすめです。
外国人労働者の受け入れに関する問題は?
外国人労働者を受け入れるうえで、現状の問題点や将来的な懸念点は気になるところでしょう。 以下で、考えられる2つの問題を具体的に解説します。
外国人労働者に対する認識が適切でない場合がある
外国人労働者の受け入れに関する問題として、認識の誤りが挙げられます。 さまざまな法整備が行われた現在では、外国人労働者の給与は日本人と同じ同等で最低賃金を超えていなければの水準でなければなりません。 最低賃金は国籍に関係なくすべての労働者に適用されるため、外国人労働者にも日本人労働者と同程度の賃金を支払うことが義務づけられています。 また、外国人労働者と日本人が同様の業務に従事する場合、賃金に差をつけることは禁止されています。 法律が整備される以前は、外国人が安価な労働力の対象としてみられていたケースもありますが、法整備後はまったく異なるため、認識を改める必要があるのです。 また、外国人労働者のなかには、専門性の高いスキルや幅広い知識を持つ方もいます。 外国人労働者をひとくくりに考えるのではなく、一人ひとりの能力に対して適切な賃金を検討しなければ、優秀な人材に巡り合うのは難しいでしょう。
最適な労働環境を整えられない可能性がある
外国人労働者が働きやすい環境が整備されていないことも、問題視されています。 日本人の働き手が集まらず、慢性的な人手不足に悩む業界では、労働時間や安全・衛生などの観点で、外国人にとっても働きづらい環境といえるかもしれません。 また、慣れない土地で働く外国人労働者には、精神的なケアや生活面でのサポートがも必要です。 業務や日常生活で問題を抱えた外国人は、早期離職してしまう可能性が高いため、最適な労働環境を整えることが急務といえるのです。
外国人労働者の受け入れに際して押さえておきたいポイント
外国人労働者を雇用する際は、快適に働ける職場環境を整備する必要があります。 そのために押さえておきたいポイントを紹介しますので、参考にしてください。
ポイント①外国人労働者に適用されるルールや手続きを覚えておく
外国人の採用を考えるのであれば、就労時のルールや必要な手続きを把握しておきましょう。 外国人労働者が日本国内に滞在するには、在留資格が必要です。
在留資格には数種類あり、資格によって日本での労働が認められるかどうかが異なります。 在留資格の就労制限の確認を怠り、労働資格のない外国人を雇用した場合は、不法就労になってしまうのです。
たとえば、日本の専門学校・大学で学ぶための"留学"の在留資格や、就労ビザで働く外国人の家族が申請可能な"家族滞在"の在留資格では、就労は許可されていません。
これらの在留資格を持つ外国人が日本で働くためには、"資格外活動の許可"を申請する必要があります。
このように、外国人労働者に関わるルールを把握しておかないと、気づかぬうちに法律に反する可能性があるので注意が必要です。
ポイント②フォロー体制を整える
外国人労働者をスムーズに受け入れるためには、企業側がフォロー体制を整えておく必要があります。 就労に関する手続き以外にも、住居の賃貸契約や銀行口座の開設といった、日本での生活に伴う手続きのサポートが必要です。
また、社内ルールの共有や日本語学習の支援といった、職場環境においてのフォローも欠かせません。
ポイント③異文化を理解する
日本とは異なる文化的背景を持っている外国人労働者を迎え入れる際は、その違いを理解することが大切です。 たとえば、日本では連続して休みを取るのは良くないこととされる風潮がありますが、海外の場合、長期休暇を取ることは珍しくありません。
また、宗教上のルールや価値観を尊重することも求められます。日本ではなじみのない文化を理解し、受け入れることが、外国人労働者を雇用するうえで重要なポイントといえるでしょう。
外国人労働者が取得している在留資格で多く利用されているもの
日本の在留資格は全部で29種類あり、そのうち定められた範囲で就労が認められる在留資格が20種類、制限なく就労できる在留資格は4種類あります。
このように数多くある就労系の在留資格のなかで、特に利用されることが多いのが、"技術・人文知識・国際業務(技人国)"です。 この資格は、外国人当人の学歴または実務経験の専門性が、業務内容と関連がある場合に認められます。
技人国の在留資格が認められる学歴要件は、以下の通りです。
【 技人国の学歴要件】
- ・本国の大学・短大・大学院を卒業している
- ・日本の大学・短大・大学院を卒業している
- ・日本の専門学校を卒業している
上記の"卒業"とは、卒業相当の学位・称号を取得している状態と同義です。 たとえば、実際に大学や専門学校を卒業していなくても、学士や学位、また専門士を取得していれば問題ありません。
ただし、専門学校の場合は、日本国内の学校のみが対象であることにご注意ください。 また、上記のような学歴がなくても、以下に当てはまる場合は技人国の申請が可能です。
【技人国の学歴以外の要件】
- ・実務経験
"技術、人文知識"の業務において10年以上の実務経験がある
"国際業務"において3年以上の実務経験がある - ・情報処理技術の資格の資格
情報処理技術の資格を取得している
上記の情報処理技術の資格とは、日本の"情報処理安全確保支援士試験"や"情報処理技術者試験"をはじめ、アジア各国で取得できる情報処理技術関連の資格を指します。
このように、技人国は、外国人労働者が学校や実務で学んだことを活かして働きたい場合に最適な在留資格です。 そのため、日本での長期的な就労を考えている外国人に多く利用されていると考えられます。
外国人労働者の受け入れに関する動き
国内の労働力不足を補うためには、外国人労働者の受け入れが欠かせません。 しかし現状、外国人労働者の受け入れに関する制度は、外国人にとって不利な内容であることが問題視されています。
ここからは、外国人労働者を受け入れるための国内の動きを解説します。
育成就労制度とは
育成就労制度とは、外国人材の育成と確保を目的とした制度です。 現行の技能実習制度に代わる新たな制度として、2027年6月までに切り替わります。
技能実習制度は、人材育成のみを目的とした制度です。 しかし、この制度を利用した技能実習生を、実質的な労働力として扱うケースが散見されたため、制度の見直しが実施されることになりました。
技能実習制度との違い
これから施行予定の育成就労制度と現在の技能実習制度には、どのような違いがあるのでしょうか。
下表に項目ごとの違いをまとめましたので、ご一読ください。
育成就労制度と技能実習制度の違い
|
|
育成就労制度 |
技能実習制度 |
|
目的 |
人材確保・人材育成 |
国際貢献・途上国への技術継承 |
|
受入れ可能な職種 |
特定技能と同じ幅広い職種 |
細分化されて限定的 |
|
在留期間 |
基本は3年 |
1号は1年、2号は2年、3号は2年(通算5年間) |
|
転籍 |
同一企業で1年以上働いたのちに可能 |
原則不可 |
|
保護・支援 |
外国人技能実習機構を改編、外部監査人が入る監理支援機関など |
外国人技能実習機構、国際人材協力機構、監理団体との連携 |
|
在留資格 |
育成就労 |
技能実習 |
|
特定技能への移行 |
移行分野・職種が一致し、かつ試験に合格すれば可能 |
移行分野・職種が一致しない限り不可 |
|
民間の職業紹介業者の介入 |
不可 |
可能 |
上記のように、2つの制度は目的や受け入れ可能な職種、在留期間などが根本的に異なる点を、理解しておきましょう。
特定技能制度との関係
育成就労制度は、在留資格"特定技能"へ速やかに移行できるように整えられた制度といえます。 特定技能とは、国内で人材を確保するのが難しい"特定産業分野"において、専門知識や技能をもつ外国人の受け入れを目的とした在留資格です。
特定産業分野は、介護や工業製品製造業、建設など全部で16分野あります。 これまでの技能実習制度では、上記のような特定産業分野で経験を積んだにもかかわらず、特定技能への移行が対象外になるケースがありました。
特定技能への移行を前提とした育成就労制度が施行されることで、このような不条理がなくなり、外国人労働者を長期的に育成・確保できるようになります。
外国人労働者の受け入れが増加しているからこそ役に立つ仕事
前述の通り、日本は外国人労働者を積極的に受け入れるための制度を整えて、国内の労働力不足に備えています。 将来的には、外国人労働者の需要がさらに高まることが予想されますが、彼らが日本企業で働くためには、ある程度の日本語スキルが求められるでしょう。
そこで重要視されているのが、日本語教師の存在です。 日本語教師は、日本語学校・大学・専門学校の授業や技能実習生向けの日本語講習などで幅広く活躍し、日本のグローバルな労働力を育む一翼を担います。
外国人労働者の受け入れが増えつづけているからこそ、日本語教師は将来的に役に立つ職業なのです。
外国人労働者の受け入れの現状から、日本語教育の重要性も高まる
今回は、外国人労働者の受け入れの現状と、雇用するメリット・デメリットを紹介しました。 日本の労働力不足を解消するために、外国人労働者を受け入れることで、採用コストの削減や自社のグローバル化の促進といったメリットを得られます。
企業は、外国人労働者の増加に伴い、就業や生活をフォローできる体制を強化する必要があります。 外国人へのサポートの一環として、日本語教育の実施を検討している企業の担当者様には、【ルネサンス日本語学院の外国人社員向け日本語研修】がおすすめです。
経験豊富な講師陣が実務で役立つ日本語をわかりやすく指導いたします。 オンライン研修も充実しており、場所や時間に縛られず学べるのが魅力です。
この記事の監修者

ルネサンス日本語学院 日本語教師養成講座講師
《資格》日本語教師養成課程修了・日本語教育能力検定試験合格
《経歴》日本語教師養成講座を修了後、約30年に渡り、大使館、留学生、インターナショナルスクール、企業などで日本語教育に従事。また、(社)国際日本語普及協会の「地域日本語教育コーディネーター研修」修了後は、地域の日本語教育、ボランティア支援や教育委員会日本語研修プログラム、NHK文化センター、一部上場企業などへの日本語教育コーディネイトや日本語教師養成に携わり、日本語教育総合支援など多方面で活躍中。
《専門分野》就労者・生活者・年少者に対する日本語教育。
《監修者からのコメント》
日本語教師の勉強は、「知識」だけでも、「技術」だけでもだめです。 両方揃って初めて「学習者」という同乗者が安心して授業を受けられます。単なる知識の講座ではなく、皆さんより少し先を歩く私たち現役日本語教師が考え、悩み、苦労してたどり着いた答えを多く取り入れた「現場目線」を意識しています。
私自身、国語教師を目指し、日本語の文法にも自信があったにもかかわらず、「こんにちは。」の使い方を外国人に教えられなかった…というショックから、「日本語」に興味を持ち、日本語教師になりました。日本語教育業界は、わかりやすそうでわかりにくいですから、この業界の専門知識のある人に相談することがおすすめです。ぜひお気軽にお問い合わせください。
- 日本語教師になる第一歩はこちら 資料請求
- 専任の担当者が回答します 個別相談・お問い合わせ
電話でのお問い合わせ・ご相談はこちら
※学院生の皆様はマイページ
「事務局への質問」から
お問い合わせください。
平日・土曜 9:30-18:00