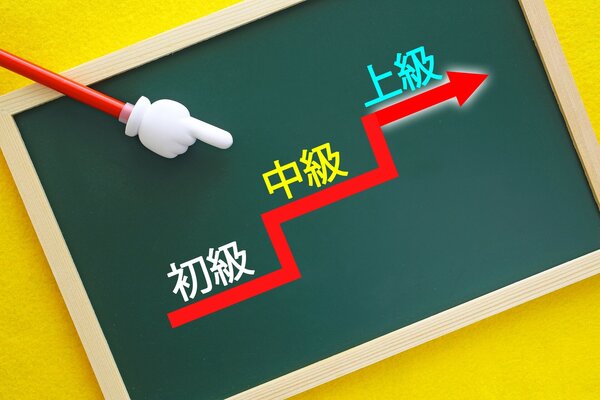日本語教師養成コラム
日本語能力試験(JLPT)とは?合格するための対策方法も解説
公開日:2025.07.25 更新日:2025.08.05

監修者情報
ルネサンス日本語学院 日本語教師養成講座講師
外国人の雇用をお考えの企業様にとって「日本語での会話に支障はないか」という点は、非常に気になるのではないでしょうか。
そのようなとき、日本語検定試験の合格の有無を確認すれば、応募者の日本語スキルをある程度測ることができます。
本記事では、外国人の採用で重要な判断材料となる日本語能力試験が、どのようなものなのかを徹底的に解説します。
今後の採用活動でよりよい人材と出会うために、ぜひ最後までご覧ください。
日本語能力試験とは
日本語能力試験(JLPT)とは、国際交流基金と日本国際教育支援協会が共催で実施する、日本語を母語としない人の日本語の能力を測定し、認定することを目的とした試験です。
試験の内容は、言語知識・読解・聴解の3つの要素で構成されており、これにより総合的な日本語のコミュニケーション能力を測っています。
N1~N5のレベルがあり、受験者の日本語の習熟度に合わせて試験の難易度を選択できるのが特徴です。
1984年の開始当初は受験者数が全世界で7,000人ほどでしたが、2018年には100万人を突破、直近の2024年には全世界で約172万人の応募があり、過去最多を記録しています。
受験者数・応募者数が、これほどまでに増加している理由は、合格によって日本での就職や資格認定などに有利にはたらくためです。
実際に、外国人を雇用する企業では、日本語能力試験の合格を応募の条件として定めているところが多く、日本語の習熟度を測る指標として広く認知されています。
日本語能力試験と日本語検定は何が違う?
日本語能力試験と混同されがちな試験に、"日本語検定"があります。
この2つをきちんと区別できるように、それぞれの違いを解説します。
そもそも日本語検定とは
日本語能力試験と日本語検定の違いの解説に移る前に、そもそも日本語検定がどういうものなのかを押さえておきましょう。
日本語検定とは、日本語を使用するすべての人が受検可能で、正しい日本語の使用を促進することを目的とした検定です。
受検者は検定の勉強を通じて、日常生活でよく使われる日本語の誤解や誤認をなくし、基礎から応用まで、日本語に関する幅広い知識とスキルを身につけられます。
学生の受験が多く、大学入学の面接や就職活動での自己アピールのために日本語検定を取得する方もいます。
日本語能力試験と日本語検定の違いとは
日本語能力試験と日本語検定では、試験あるいは検定を受けられる対象者が異なります。
日本語能力試験では基本的に、"日本語を母語としない人"を対象としています。
外国人であっても、幼少期から日本語を使用している人は、同試験を受けられません。
反対に、日本人でも、海外で生まれ育ち、幼少期に日本語を使う機会がなければ試験を受けることが可能です。
一方、日本語検定は、"日本語を使うすべての人"が対象です。
日本語を母語とする人もしない人も、誰でも受検することができます。
こうした対象者の違いのほかにも、日本語能力試験と日本語検定とでは目的も異なります。
日本語能力試験の目的が"日本語スキルの客観的な証明"であることに対して、日本語検定の目的は"日本語スキルの向上"です。
日本語能力試験は、外国人が「日本語を習熟している」ということを、第三者に証明できる試験であるからこそ、日本での就職や資格認定などで有利にはたらくのです。
日本語能力試験が実施される時期や場所は?
日本語能力試験は、毎年7月と12月の年2回、日本国内および世界各国の主要都市で実施されています。
試験が行われるのは基本的に、日本国内では全国47都道府県、海外では249都市です。
しかし、会場の借用状況や災害の影響によっては、希望する会場とは異なる場所になったり、試験自体が中止されたりする可能性があります。
試験の時期や場所についての最新情報は、日本語能力試験の公式Webサイトで公開されているので、そちらを適宜確認することをおすすめします。
申し込み方法
日本国内で日本語能力試験の受験を希望する方は、スマートフォンやタブレットから、オンラインで簡単に申し込むことができます。
今回は、個人が日本国内で受験する場合の申し込み方法を紹介します。
採用予定の外国人が受験を希望している際には、ぜひサポートしてあげてください。
個人が日本国内で受験する場合の申し込みの流れ
- ①MyJLPTへ登録
- ②MyJLPT IDの取得
- ③MyJLPTへログイン
- ④受験申込情報の登録
- ⑤受験料の支払い
- ⑥受験申込みの完了
まずは、日本語能力試験の公式Webサイトから"MyJLPT IDに登録"に進み、MyJLPT IDを取得しましょう。
MyJLPT IDを取得したら、MyJLPTへログインし、受験者申し込み情報を登録します。
次に、受験料の支払いへと進みます。
支払い方法は、クレジットカードでの支払い・銀行振り込み・コンビニエンスストアでの支払いの中から選ぶことが可能です。
受験料の支払いを終えたら、受験の申し込みが完了です。
なお、MyJLPT IDの取得時にご自身で設定したパスワードと、申し込み完了時に発行された"申込受付番号"は、忘れないようにきちんと保管しておく必要があります。
日本語能力試験のレベル
ここからは、日本語能力試験のレベルについて詳しく解説していきます。
外国人の雇用をお考えの企業様は、応募者がどのくらい日本語を習熟しているのかを、把握するための判断材料としてお役立てください。
なお、以下の内容はすべて、日本語能力試験の公式Webサイトの情報に基づいて記載しています。
N1
N1は、日本語能力試験のなかで、もっとも難易度の高いレベルです。
合格者は幅広いシーンで使用される日本語を理解し、かつ、さまざまな表現の仕方を習熟していると評価されます。
"読む"と"聞く"の言語行動で表した、認定の目安は以下の通りです。
N1の認定の目安
|
言語行動 |
認定の目安 |
|
読む |
・ 論理的に書かれた複雑な文章や、抽象度の高い文章を理解できる ・ 内容に深みのある読み物を読んで、話の流れや詳細な表現意図を理解できる |
|
聞く |
まとまりのある会話やニュース、講義を自然なスピードで聞いて、話の流れや内容の論理構成、登場人物の関係などを詳細に理解できる |
N1は、日常会話にくわえて、敬語や丁寧語、ビジネス会話も理解している必要があり、日本語を母語とする日本人でさえも満点を取るのは難しいといわれています。
N2
N2の合格者も、N1と同様、実生活のさまざまな場面において使われる日本語を体得しているレベルです。
以下は、言語行動におけるN2の認定の目安です。
N2の認定の目安
|
言語行動 |
認定の目安 |
|
読む |
・ 新聞や雑誌の記事、解説、平易な評論など、論旨が明快な文章を理解できる ・ 一般的な話題に関する読み物を読んで、話の流れや表現意図を理解できる |
|
聞く |
まとまりのある会話やニュースを自然に近いスピードで聞いて、話の流れや内容、登場人物の関係を理解できる |
N2に合格していれば、日常会話だけでなく、ビジネスシーンや専門的なやり取りが行われる場面での会話も、ある程度理解できると考えてよいでしょう。
N3
5段階のレベルのちょうど中間にあり、ほかのレベルとの"橋渡し"として位置づけられているのがN3です。
合格者は日常会話で使用される日本語を、ある程度は理解できるとみなされます。
N3における言語行動ごとの認定の目安は、以下をご参照ください。
N3の認定の目安
|
言語行動 |
認定の目安 |
|
読む |
・ 日常的な話題について書かれた文章を理解できる ・ 新聞の見出しから情報の概要を掴むことができる ・ 難易度がやや高い文章については、言い換え表現を与えられれば理解できる |
|
聞く |
まとまりのある会話を、やや自然に近いスピードで聞き、話の内容や登場人物の関係などをある程度理解することができる |
N3の段階では、知っている文法や単語がそれほど多くありません。
そのため難しい言葉は表現を換えて伝える必要がありますが、言い換えさえすれば、コミュニケーションを十分に取ることができます。
N4
N4は、基本的な日本語を理解することのできるレベルです。
言語行動で表した認定の目安は、以下のように設定されています。
N4の認定の目安
|
言語行動 |
認定の目安 |
|
読む |
基本的な語彙や漢字を使って書かれた文章を理解できる |
|
聞く |
日常的な場面において、ややゆっくりと話される会話であれば、内容がほぼ理解できる |
N4レベルの方が習得している単語は、基本的なもののみであるため、N3と同じように難しい言葉は置き換える必要があります。
日常会話においては、ゆっくりとした速度で、かつ基本的な単語を使って話せば理解することが可能です。
N5
N5は、日本語能力試験でもっとも難易度の低いレベルです。
それでも基本的な日本語であれば、ある程度理解することができます。
N5の認定の目安は、以下をご覧ください。
N5の認定の目安
|
言語行動 |
認定の目安 |
|
読む |
ひらがなやカタカナ、平易な漢字で書かれた定型的な文章を理解できる |
|
聞く |
日常生活において、ゆっくり話される短い会話であれば、必要な情報を聞き取ることができる |
N5を合格した段階では、知っている文法や単語が少ないことから、会話の意味がわからずに返答に行き詰まってしまうこともあるかもしれません。
しかし、教科書で習う定型文に関してはよく理解できているため、日常的な挨拶や簡単な自己紹介であれば行えます。
日本語能力試験の合格基準
日本語能力試験の合格基準は、"総合得点が合格点以上であること"と"区分ごとに設けられた得点が合格点以上であること"の両方を満たしていることです。
区分ごとに設定された合格点に達していない科目が一つでもあれば、どれだけ総合得点が高くても不合格となります。
参照元:日本語能力試験「3.合否の判定」
日本語能力試験の合格率はどのくらい?
日本語能力試験の合格率は、実際にどのくらいの数値となっているのでしょうか。
以下に、2024年に実施された第1回目の試験における、レベルごとの合格率をまとめたのでご覧ください。
2024年第1回の合格率
|
|
レベル |
N1 |
N2 |
N3 |
N4 |
N5 |
|
国内 |
合格率 |
31.5% |
33.5% |
38.5.% |
44.1% |
61.8% |
|
海外 |
合格率 |
34.4% |
41.6% |
42.4% |
38.8% |
49.1% |
レベル別の合格率の推移を見てみると、おおむねレベルが上がるにつれて合格率が下がっていることがわかります。
特にN1は、「日本人が受験しても満点を取るのは難しい」といわれているだけあり、おおよそ3人に1人の合格にとどまっています。
参照元:日本語能力試験「2024(令和6)年第1回(7月)データ」
日本語能力試験に合格するメリット

ここからは、日本語能力試験の合格者にもたらされる3つのメリットを紹介します。
企業側から見たメリットも解説しているので、そちらもあわせてご確認ください。
メリット①就職時のアピールポイントになる
最難関であるN1・N2の合格は、日本で就職を目指す外国人にとって、大きなアピールポイントとなります。
外国人を雇用する企業では応募者の日本語スキルを評価するために、多くの場合、日本語能力試験の結果を参考にしています。
そのためN1・N2に合格すれば、こうした企業に対して、ビジネスシーンでも円滑にコミュニケーションを取れることを証明できるのです。
また、日本語能力試験に合格したという事実は、これまで長期間にわたり、努力して学習を続けてきた証拠でもあります。
企業側からすれば、応募者が、日本語スキルを持っているだけでなく、粘り強く努力を続けられる人材であると判断できます。
メリット②在留資格を取得できるようになる
日本語能力試験に合格すれば、在留資格の一つである"特定技能"を取得するための要件を、一部満たせます。
そもそも在留資格がどういうものなのかというと、これは、外国人が日本に滞在しながら、なんらかの活動を行うために必要となる資格のことを指します。
在留資格にはいくつかの種類があり、そのなかで、特定の分野の業務に従事するために必要になるのが特定技能です。
日本での就職を考えている外国人が、在留資格の特定技能を取得するには、仕事をスムーズに進められる日本語スキルを持っていることを証明する必要があります。
このとき、その証明となるのが、日本語能力試験のN4以上の合格というわけです。
企業側は、日本語能力試験のN4以上に合格しており、かつ特定技能を取得している外国人なら、一定の専門的なスキルを持ち、即戦力になりえると考えます。
実際、このレベルの外国人であれば、従業員として迎え入れても、日本人と遜色ない能力を発揮できる可能性が高いといえるでしょう。
メリット③日本で資格を取得できるようになる
日本で国家試験を受ける際、受験資格の要件を満たすことができる点も、日本語能力試験に合格するメリットの一つです。
日本語能力試験のN1は、医師や看護師、薬剤師といった国家試験を受ける際の、受験資格の要件として定められています。
日本語能力試験N1は、海外で取得した医療系資格を日本で認定するために必要になります。
【認定に日本語能力試験N1が必要となる医療・看護関係の国家資格】
- ・歯科医師
- ・歯科衛生士
- ・歯科技工士
- ・看護師
- ・薬剤師
- ・保健師
- ・助産師
- ・診療放射線技師
- ・臨床検査技師
- ・理学療法士
- ・作業療法士
- ・視能訓練士
- ・臨床工学技士
- ・救命救急士
- ・言語聴覚士
- ・獣医師
- ・愛玩動物看護士
日本語能力試験の注意点
外国人の雇用をお考えの企業様にとって、応募者の日本語スキルというのは、採用の可否を決める重要な判断材料です。
そこで習熟度を測るための指標となるのが、日本語能力試験の合格の有無というわけですが、ただ単に結果だけを見て採用するとミスマッチが生じてしまう可能性があります。
以下では、「もう少しコミュニケーションを取れるかと思ったが...」とがっかりする前に知っておきたい、日本語能力試験の注意点を解説します。
注意点①会話力が身についているとは限らないことを理解する
日本語能力試験に合格していても、実際に会話力が身についているとは限りません。
それは、日本語能力試験が"読む"・"聞く"に特化したマークシート方式の試験であり、"話す"については測定していないためです。
したがって、試験には合格していても、実生活における会話力は期待するレベルに達していない可能性がある点は承知しておきたいところです。
日本語能力試験の結果とともに、実際の会話力を面接時に確認すれば、どの程度話せるのかわかるので、入社後にやり取りで苦労する場面も減るでしょう。
注意点②受験者によって日本語のレベルに違いがある
同じレベルの合格者であっても、受験者によって日本語のレベルに違いがある点も覚えておきたいところです。
繰り返しになりますが、日本語能力試験では、言語行動における"読む"と"聞く"の能力を主に測っており、"話す"と"書く"については測定されません。
そのためどうしても、実際の会話力やコミュニケーション能力には個人差が出てしまうのです。
応募者の日本語のレベルをできる限り正確に把握するには、面接時の会話で判断する以外にも、企業独自の簡単な書き取りテストを作成してみてもよいでしょう。
日本語能力試験の代替になる試験はある?
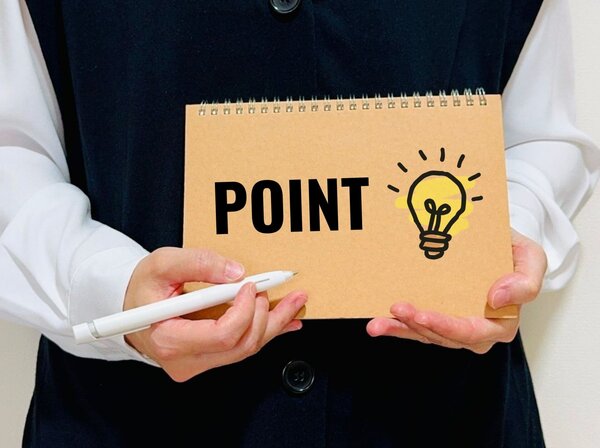
実は日本語能力試験のほかにも、日本で就業・就学する際の日本語スキルの証明として、法務省に認められている試験がいくつか存在します。
そのなかから今回は、"JPT日本語能力試験"と"J.TEST実用日本語検定"について詳しく解説します。
JPT日本語能力試験
JPT日本語能力試験は、日本語能力試験と同様、日本語を母語としない人を対象として日本語スキルの客観的な測定・評価を目的とした試験です。
JPT日本語能力試験の概要
|
実施機関 |
一般社団法人 日本語能力試験実施委員会 |
|
目的 |
ビジネスを含む日常的な場面や状況において、高度で機能的なコミュニケーション能力を客観的に測定・評価すること |
|
実施地 |
国内:東京都・大阪府・愛知県などの主要都市 海外:アジアを中心とした13か国 |
|
評価方法 |
990点満点の無段階評価 |
|
実施回数 |
年12回 |
|
受験料 |
国内:7,700円 海外:実施地によって異なる |
|
評価を行う言語能力 |
読む・聞く |
日本語能力試験とJPT日本語能力試験のレベルの対比は、以下の通りです。
【日本語能力試験とJPT日本語能力試験のレベルの対比】
|
日本語能力試験 |
JPT日本語能力試験 |
|
N1 |
660点以上 |
|
N2 |
525点以上 |
|
N3 |
430点以上 |
|
N4 |
375点以上 |
|
N5 |
315点以上 |
JPT日本語能力試験の評価方法は、合否判定ではなく点数制のため、日本語のレベルを数値化して把握できます。
J.TEST実用日本語検定
J.TEST実用日本語検定は、就業や就学などの場面で必要となる、実用的かつ実践的な日本語の能力を測る検定です。
日本語能力試験やJPT日本語能力試験と同じように、日本語を母語としない人を対象としています。
J.TEST実用日本語検定の概要
|
実施機関 |
日本語検定協会/J.TEST日本事務局 株式会社語文研究社 |
|
目的 |
実用的かつ実践的な日本語スキルを測定すること |
|
実施地 |
国内:東京都・大阪府・愛知県・福岡県などの主要都市 海外:13か国(地域) |
|
評価方法 |
A-Cレベル:1,000点満点の600点以上で認定 D-Eレベル:700点満点の350点以上で認定 F-Gレベル:350点満点の180点以上で認定 |
|
実施回数 |
A-CおよびD-Eレベル:年6回 F-Gレベル:年2回(日本国内) |
|
受験料 |
国内:5,800円(中学生と高校生は2,900円) 海外:実施地によって異なる |
|
評価を行う言語能力 |
読む・聞く・書く |
日本語能力試験とJ.TEST実用日本語検定のレベルの対比を、以下の表にまとめたのでご確認ください。
日本語能力試験とJ.TEST実用日本語検定のレベルの対比
|
日本語能力試験 |
J.TEST実用日本語検定 |
|
N1 |
A-Cレベル700点以上 |
|
N2 |
A-Cレベル600点以上 |
|
N3 |
D-Eレベル500点以上 |
|
N4 |
D-Eレベル350点以上 |
|
N5 |
F-Gレベル250点以上 |
J.TEST実用日本語検定では、短文の作成や漢字の読み方など、日本語能力試験にはない記述式の問題があるので、日本語に関するより深い知識が問われることになります。
日本語能力試験以外にも日本語に関する試験はあるのか
日本語能力試験および、その代替となる試験のほかにも、日本語スキルを測る試験はいくつもあります。
以下では、数ある試験のなかから3つの試験・検定を紹介します。
日本語NAT-TEST
日本語NAT-TESTは、試験の構成が日本語能力試験とほぼ同じなため、日本語能力試験の事前対策として受験されることもある試験です。
日本語NAT-TESTの概要
|
実施機関 |
専⾨教育出版 ⽇本語NAT-TEST運営委員会 |
|
目的 |
⽇本語スキルを測定すること |
|
実施地 |
国内:東京都・大阪府 海外:16か国 |
|
実施回数 |
年6回以上 |
|
受験料 |
国内:5,500円 海外:実施地によって異なる |
|
評価を行う言語能力 |
読む・聞く |
就業や就学において、日本語能力試験だとタイミングが合わないときは、この試験を受けて日本語スキルの証明とすることがあります。
参照元:日本語NAT-TEST「日本語NAT-TESTについて」
BJTビジネス日本語能力テスト
BJTビジネス日本語能力テストは、日本での就職をお考えの方はもちろん、基礎的な日本語を体得した方がさらなるステップアップのために受けるパターンが多くみられる試験です。
BJTビジネス日本語能力テストの概要
|
実施機関 |
公益財団法⼈⽇本漢字能⼒検定協会 |
|
目的 |
ビジネスシーンで必要とされる⽇本語のコミュニケーション能⼒を測定すること |
|
実施地 |
国内:50都市 海外:20か国 |
|
実施回数 |
ほぼ毎日実施、ただし1度受験すると次の受験まで3か月空ける必要がある |
|
受験料 |
国内:7,000円 海外:実施地によって異なる |
|
評価を行う言語能力 |
読む・聞く |
ビジネスシーンでも十分に通用する日本語スキルを持っていると証明したい方は、BJTビジネス日本語能力テストに挑戦してみる価値はあるといえます。
実践日本語コミュニケーション検定・ブリッジ(PJC Bridge)
日本語を母語としない外国人を対象として、日本で就業する際に必要とされる日本語スキルを測定するのがPJC実践日本語コミュニケーション検定です。
PJC実践日本語コミュニケーション検定の概要
|
実施機関 |
株式会社サーティファイ コミュニケーション能⼒認定委員会 |
|
目的 |
日本で就業する際に必要とされる日本語のコミュニケーション能力を測定する |
|
実施地 |
団体受検:自校・自社で実施 |
|
実施回数 |
団体受検:自由に設定可能 |
|
受験料 |
国内:4,600円(Web試験) 5,200円(ペーパー試験) 海外:実施地によって異なる |
|
評価を行う言語能力 |
読む・聞く |
上司や同僚との会話力、接客能力、ビジネスマナーなどの習熟度を深めたい方には、PJC実践日本語コミュニケーション検定の受検がおすすめです。
参照元:PJC実践日本語コミュニケーション検定「PJC Bridgeとは」
日本語能力試験に合格するためのポイント
ここからは、日本語能力試験に合格するためのポイントを解説します。
自社で雇用した外国人が、これから日本語能力試験を受けようとしている場合は、以下で紹介する内容をアドバイスしてみてください。
ポイント①試験範囲をきちんと把握する
日本語能力試験に合格するには、試験範囲をきちんと把握することが第一歩です。
日本語能力試験の試験科目は、言語知識(文字・語彙・文法)、読解、聴解です。
それぞれの試験範囲をまんべんなく俯瞰的に把握すれば、合格に必要なスキルが明確になり、効率的な学習計画を立てられるようになります。
試験範囲を把握するには、日本語能力試験の公式Webサイトで公開されている問題例や、紹介されている教材を用いて各レベルの内容や出題形式を確認するとよいでしょう。
ポイント②目標から逆算し、最適な学習プランを立てる
試験範囲を確認したら、学習プランを立てることも忘れてはなりません。
学習プランを立てる際は、目標とするレベルの学習時間と、受験者自身が1日に確保できる学習時間のバランスを考慮しながら、スケジュールに落とし込むのがおすすめです。
ただし、ここで気をつけたいのが、試験日までの期間が長くなるほど途中で挫折する可能性が高くなるということです。
学習のモチベーションを維持するためには、短期的な目標(マイルストーン)を立てて、定期的に達成感を得られる機会を設けましょう。
「いつまでに教材を終わらせる」「この日に模擬試験に挑戦する」といったように、区切りとなる日にちを事前に決め、メリハリのある学習プランを作成することが肝要です。
ポイント③問題を何度も解く
日本語の知識がある程度定着したら、試験本番での対応力を高めるために問題を繰り返し解きましょう。
言語知識(文字・語彙・文法)、読解、聴解のなかに苦手な科目があれば、その科目を中心に問題を解くのも一つの手段ですが、特におすすめしたいのが過去問の反復です。
過去問は、3回以上の実践を目標とし、2回目以降は正答率が8~9割を超えることを目指してみてください。
こうすることで、出題傾向を掴めて効率的な試験対策が可能になりますし、本番を想定した時間配分や解答スピード、さらには合格できる実力も鍛えられます。
項目別!日本語能力試験の対策のコツ
続いて、科目別の日本語能力試験の対策方法を解説します。
もしも、学習方法に行き詰っている受験者が採用予定者にいたら、以下で紹介するコツを伝えてあげてください。
文字・語彙の場合
文字・語彙の分野では、試験範囲の漢字や語句などを覚えることがまず大切です。
このとき、教材を読んで暗記するだけでなく、ノートに書き写したりフラッシュカードを用いて繰り返し確認したりすることで、より正確に知識が定着します。
ただし、漢字や語句とその母語訳を1対1で覚えるだけでは、"言い換え類義"や"用法"の問題で苦戦する可能性があります。
このような問題をスムーズに解くためにも、漢字や語句を覚える際は、同義語・対義語・類語などをグループ化して覚えるとよいでしょう。
また漢字や語句の意味だけでなく、自然な使い方を一緒に理解することで、用法の問題の対策にもつながります。
文法の場合
文法の問題の対策には、まず文法理解が欠かせません。
日本語を学ぶ外国人にとって、自動詞と他動詞の違いや、敬語、受け身の表現などは特に難しいといわれています。"て・に・を・は"といった助詞も使い分けが難しく、苦手意識を持っている方が多いようです。
文法の問題を解く力を伸ばすには、自然な日本語の文章に慣れることが何より大切です。
なるべく多くの問題を解き、意味のわからない文法を一つひとつ入念に調べれば、おのずと日本語スキルも身についてくるでしょう。
読解の場合
読解の分野では、日本語の本や新聞を読み、日本語ならではの表現や文脈を理解することがよいでしょう。
具体的な方法としては、本や新聞、Webニュースの内容を100字程度で要約したり、映画の感想を数行でまとめたりするのがおすすめです。
これにより、文章全体の流れを素早く理解できる力が身につくため、試験本番においても、問題文を効率よく整理し、正しい答えを導きやすくなります。
また、こうした日々の練習に加えて、出題される文章の形式に応じた解き方のコツを押さえておくことも重要です。
たとえば、対比・言い換え・比喩のように各役割に分類することで、スピーディーに読み解けます。
聴解の場合
聴解の問題を対策するには、ニュースやラジオ、映画などを聞き、日本語の音声に慣れることが大切です。
その際、"シャドーイング"や"ディクテーション"を同時に行うと、より効率的に聴解の問題の対策を打てます。
シャドーイングとは、音声のあとにつづいて復唱する勉強方法のことで、これにより音声知覚を鍛え、正確に聞き取れる力を養えます。
ディクテーションは、聞いた音声を書き取るトレーニングです。
聞き取れた音声を一言一句書き出さなければならないため、シャドーイングよりも難易度が上がりますが、聴解力を鍛えるには非常に効果的な方法の一つに挙げられます。
日本語を聞き取るスキルを身につけるには、自然な速度で話される日本語に耳を慣れさせることが重要です。
上記で紹介した方法を活用しつつ、より多くの日本語の音声に触れるようにしましょう。
日本語能力試験の対策はどこで行っている?
日本語能力試験は、日本語学校やオンラインの日本語学習サービスなどで、対策講座を受けることが可能です。
日本で働く外国人にとって、日本語能力試験は非常に重要な試験ですが、仕事をしながら勉強するとなると、なかなか効率的に学習できないこともあるでしょう。
そんなときは、日本語学校やオンラインの日本語学習サービスなどを活用して、日本語に関する知識やスキルを身につけることもできます。
担当の講師と共に、受験者自身に合った学習プランを立てれば、効率的な学習が実現し、日本語能力試験の合格に近づけるはずです。
日本語能力試験とは、日本語を母語としない人の日本語スキルを測る試験!

今回は、日本語能力試験について徹底的に解説しました。
日本語能力試験とは日本語を母語としない人の日本語の能力を測定し、認定することを目的とした試験です。
外国人を雇用する企業では、応募者の日本語の習熟度を測る指標として広く認知されています。
ただし試験に合格していても会話力が身についているとは限らないため、実際のコミュニケーション能力については面接時に確かめることをおすすめします。
また、外国人社員の日本語教育においては、実践的なコミュニケーション力の習得が重要です。ルネサンス日本語学院では、業種や職種に合わせたオーダーメイド研修を提供し、効率的な学習を支援しています。
オンライン・対面いずれのスタイルも対応可能で、貴社の業務に支障なく導入できます。
興味を持たれた方はぜひ【ルネサンス日本語学院の外国人向け日本語研修】へお問い合わせください。
この記事の監修者

ルネサンス日本語学院 日本語教師養成講座講師
《資格》日本語教師養成課程修了・日本語教育能力検定試験合格
《経歴》日本語教師養成講座を修了後、約30年に渡り、大使館、留学生、インターナショナルスクール、企業などで日本語教育に従事。また、(社)国際日本語普及協会の「地域日本語教育コーディネーター研修」修了後は、地域の日本語教育、ボランティア支援や教育委員会日本語研修プログラム、NHK文化センター、一部上場企業などへの日本語教育コーディネイトや日本語教師養成に携わり、日本語教育総合支援など多方面で活躍中。
《専門分野》就労者・生活者・年少者に対する日本語教育。
《監修者からのコメント》
日本語教師の勉強は、「知識」だけでも、「技術」だけでもだめです。 両方揃って初めて「学習者」という同乗者が安心して授業を受けられます。単なる知識の講座ではなく、皆さんより少し先を歩く私たち現役日本語教師が考え、悩み、苦労してたどり着いた答えを多く取り入れた「現場目線」を意識しています。
私自身、国語教師を目指し、日本語の文法にも自信があったにもかかわらず、「こんにちは。」の使い方を外国人に教えられなかった…というショックから、「日本語」に興味を持ち、日本語教師になりました。日本語教育業界は、わかりやすそうでわかりにくいですから、この業界の専門知識のある人に相談することがおすすめです。ぜひお気軽にお問い合わせください。
- 日本語教師になる第一歩はこちら 資料請求
- 専任の担当者が回答します 個別相談・お問い合わせ
電話でのお問い合わせ・ご相談はこちら
※学院生の皆様はマイページ
「事務局への質問」から
お問い合わせください。
平日・土曜 9:30-18:00